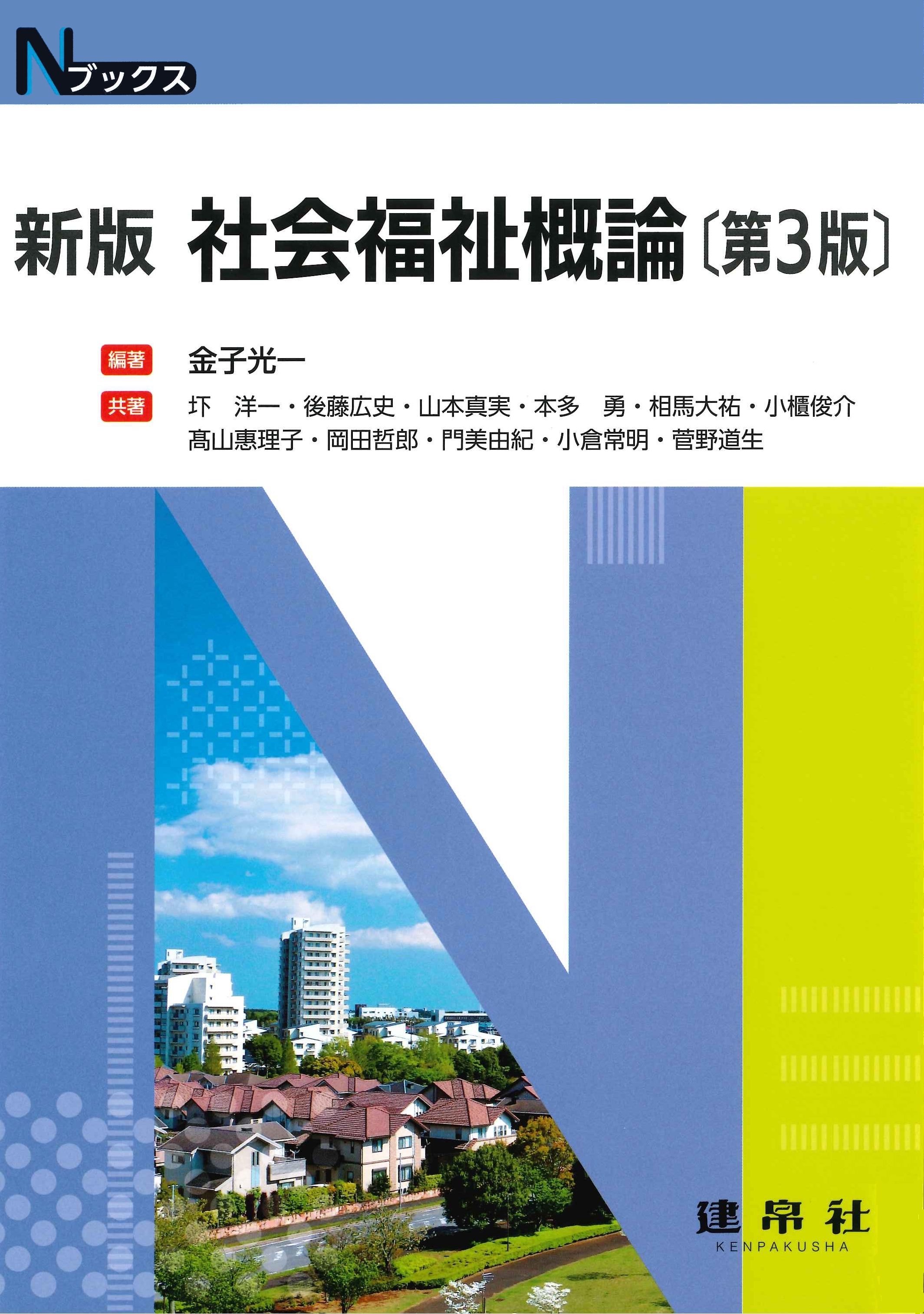栄養士・管理栄養士養成課程のための社会福祉の概論書。社会福祉の価値を理解し,社会福祉の対象とそれを取り巻くシステムを把握し,社会福祉の実践としてのソーシャルワークを学ぶことを主眼とする。それぞれの章は「基本的な考え方(理念)」「現状(法的根拠)」「課題(展望)」の三つの柱で構成されている。福祉の関連諸制度と動向を総合的に広く紹介。最新動向に沿う第3版。
内容紹介
まえがき
はじめに
本書は,管理栄養士・栄養士養成のための社会福祉の概論書として刊行されたものである。2010(平成22)年12 月,管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)が改定され,「社会・環境と健康」の中に「保健・医療・福祉の制度」が大項目として位置づけられた。「社会・環境と健康」の出題のねらいには「保健・医療・福祉制度や関係法規の概要についての基礎的知識を問う」とあり,本書はそのねらいに応えるものである。管理栄養士・栄養士を目指す学生の皆さんにぜひご活用頂きたい。また同時に,「社会福祉学概論」等関連科目を開講している大学・短期大学・専門学校においても,社会福祉の概論書として広くご活用頂けるように,社会福祉の諸制度とその動向を網羅的に紹介している。
日本の社会福祉は今,大きな岐路に立たされている。社会変動によって多様化・高度化するニード,人間本来の差異や社会構造の変化によって生じる排除や社会的格差に対して,社会福祉は何ができるのであろうか。広く人びとの生活の質の向上に貢献するために必要なことは何であろうか。
これに対して私は次のように考える。まず,社会福祉の価値を理解することである。価値を理解することによって他者と協同して,よりよい共生社会を構築することができる。第二に,対象やそれを取り巻くシステムを学修することである。生活困窮者や子ども,高齢者や障害者,介護を必要とする人びとが,どのような状況に置かれているかを理解し,個々人が抱えている諸課題を社会の問題として把握することが重要である。第三に,社会福祉の実践,すなわちソーシャルワークを学ぶことである。本書では特に重要と考える医療と地域を基盤としたソーシャルワークに限定したが,社会福祉の実践はそれにとどまるものではない。またそれぞれの実践が関係するさまざまな専門職の活動と連携していることも理解しなければならない。とりわけ保健・医療との連携は今日の社会福祉実践において核となるものである。最後に,災害等により生活の基盤を失い社会の枠から漏れてしまった人びとや,外国から日本に移住して偏見や差別を受けている人びとに対する社会資源をどのように構築するかを考えることである。これからの社会福祉は,そこで暮らす一人ひとりの生活を重視し,多様な価値観を受け入れながら展開していかなければならない。
以上の考えに基づいて,本書の構成の枠組みは,大きく「価値」「対象・システム」「ソーシャルワーク」「保健」「資源」に分けた。「価値」 にあたるのが序章および第1・2 章,「対象・システム」 にあたるのが第3 〜7 章,「ソーシャルワーク」にあたるのが第8・9 章,「保健」にあたるのが第10・11 章,「資源」にあたるのが第13・14章である。またそれぞれの章は,概ね「基本的な考え方(理念)」「現状(法的根拠)」「課題(展望)」の三つの柱で構成されている。読者の皆さんの一助となれば幸いである。
最後になったが,本書の企画趣旨をご理解頂き,執筆にご協力頂いた11 名の方々に,この場を借りて深くお礼申し上げる。
2014 年11 月
編者 金 子 光 一
新版第3 版刊行にあたって
2014 年12 月の新版発行より早いもので6 年あまりが経過した。この間,2018 年2 月に〔第2 版〕を刊行したが,さらにそれから3 年の月日が経った。本書の構成の枠組みは,初版刊行の段階で「価」「対象・システム」「ソーシャルワーク」「保健」「資源」と設定したが,今日の新型コロナウイルス感染症の拡大によって,そのすべての枠組みでこれまでとは異なる新たな対応が求められている。とりわけ,コロナのリスクと危機が,潜在化していた分断・排除・対立,社会的脆弱性などを表面化させ,深刻な社会問題となっている状況を直視しなければならない。世界が直面する危機的状況にあって,いま社会福祉は何ができるのか,果たすべき役割と価値を今一度十分に検証する必要性を痛感している。コロナ禍で顕在化した課題の多くは,コロナが収束した後の時代も残り続け,解決が求められるものである。そのことを十分認識しながら,これからの社会福祉を考えなければならない。
新版第3 版はそうしたことを意識して刊行するものである。
2021 年8 月
編者 金 子 光 一
目 次
序章 社会福祉の概念―生活者を取り巻く課題
1. 福祉マインドの涵養
2. 社会的支援システム
3. 個人と社会の関係
4. ニードの充足
5. 近年の生活問題
6. 社会福祉専門職に求められる知識・技術
第1章 社会福祉の歴史
1. 萌芽期
2. 生成期
3. 発展期
4. 成熟前期
5. 成熟後期
6. 転換期
7. 転換期以降の動き
第2章 社会保障制度の意義
1. 社会保障の意味
2. 社会保障制度像の変遷
3. 社会保障制度の仕組み
4. 社会保障制度の役割
第3章 生活困窮者のための福祉制度・施設
1. 公的扶助制度の歴史
2. 生活保護法
3. 低所得者対策
4. 第二のセーフティネット
5. 生活困窮者のための施設
第4章 子どものための福祉制度・施設
1. 子ども家庭福祉の対象
2. 子ども家庭福祉の理念と目的
3. 子ども家庭福祉の法律
4. 子ども家庭福祉の施策体系
5. 子ども家庭福祉行政の仕組み
6. 児童福祉施設の現状
7. 今後の課題と展望
第5章 高齢者のための福祉制度・施設
1. 高齢者福祉の理念―高齢者を敬い,助けるということ
2. 高齢者福祉の歴史・流れ
3. 高齢者福祉と介護の制度
4. 介護保険制度の導入
5. 高齢者のための施設
6. 今後の課題と展望
第6章 障害者のための福祉制度・施設
1. 障害者福祉の基本的な考え方
2. 障害者福祉の現状
3. 今後の課題と展望
第7章 介護を必要とする人びとと介護の概要
1. 介護の社会的意義
2. 介護の役割
3. 介護の専門性
4. 今後の課題と展望
第8章 医療ソーシャルワーク
1. 医療ソーシャルワークとは
2. 傷病・障害と生活:MSWが対象とする問題・課題
3. ソーシャルワーク実践における観点
4. 保健医療福祉の協働
5. 今後の課題と展望
第9章 地域を基盤としたソーシャルワーク
1. 基本的な考え方(理念)
2. 現状(法的根拠)
3. 今後の課題と展望
第10章 母子保健
1. 母子保健施策の対象と目的
2. 母子保健に関する法律
3. 母子保健の歩みと水準
4. 母子保健行政の仕組み
5. 母子保健施策の概要
6. 母子保健施策の方向性
第11章 地域保健
1. 地域保健が求められる理由
2. 地域保健法の制定と改正
3. 基本指針の目的と改正経緯
4. 基本指針の具体的内容―社会福祉等の関連施策との連携を中心に
5. 社会福祉関連施策にみられる福祉・保健の一体的な取り組みの促進
6. 今後の課題と展望
第12章 ボランティア(活動)
1. ボランティア(活動)とは
2. ボランティア(活動)の歴史
3. 法制度とボランティア(活動)
4. ボランティア活動の実際
5. ボランティアコーディネート
第13章 災害福祉
1. 災害と社会の脆弱性
2. 災害福祉,災害ソーシャルワークとは何か
3. 今後の課題と展望
第14章 国際協力と多文化共生
1. 国際協力
2. 多文化共生
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup
-

四訂 栄養指導論
-
-
-
pickup
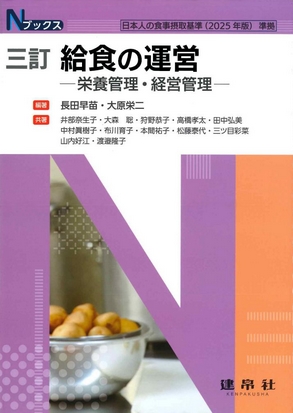
三訂 給食の運営
2024年公表の栄養士実力認定試験出題基準(ガイドライン),および日本人の食事摂取基準2025年版に準拠した給食管理の教科書。食物アレルギーについても記載する。
-
-
-
pickup

五訂 臨床栄養管理
各疾患の病態生理/栄養アセスメント・モニタリング/栄養基準/栄養食事指導等,栄養状態を評価し栄養ケア・マネジメントを実践するための知識を詳述。最新の診療・介護報酬や学びを支える巻末資料も充実。
-
-
-
pickup

改訂 応用栄養学概論
専門用語について,本文の文脈に沿った側注を掲載。初学者にも理解できるよう配慮した。日本人の食事摂取基準(2025年版)に対応した改訂版。
-
-
-
pickup
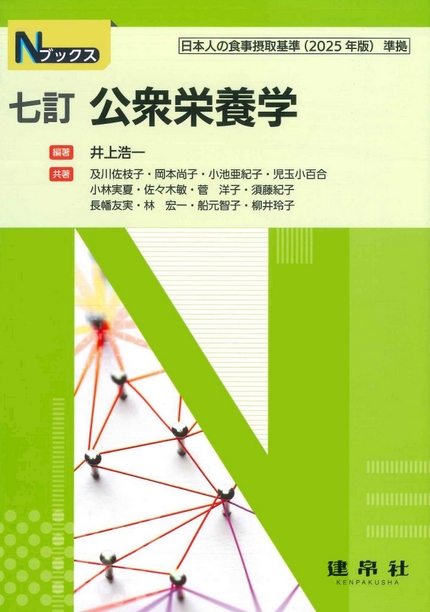
七訂 公衆栄養学
栄養士・管理栄養士養成課程教科書。令和5年国民健康・栄養調査,令和6年度食料需給表ほか最新統計,内外の最新動向に沿う。管理栄養士国家試験出題基準を網羅し,さらに内容を盛り込み、充実させた。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。