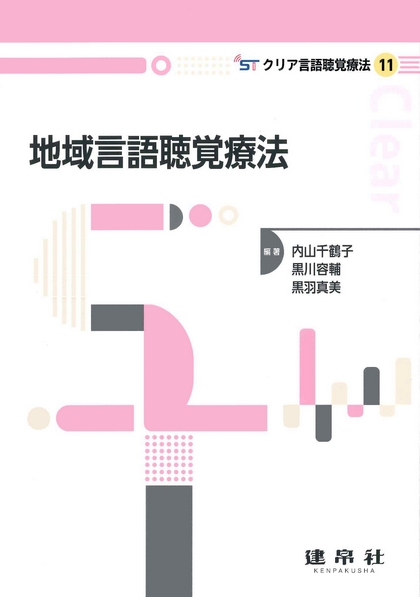新規科目「地域言語聴覚療法学」の最新テキスト。言語聴覚障害のある人とそれを取り巻くすべての人が自分の暮らす地域社会で自立した生活を送るための支援を学ぶ。成人・小児の事例からわかりやすく解説。
内容紹介
まえがき
まえがき
総務省によると,2023年の年間出生数は73万人を下回った一方,高齢者数は3,600万人以上となり,高齢化率は35%を超えた。今後も高齢者数は増加し,2040年にピークを迎えると予測されている。少子高齢化の進展を踏まえ,医療保険や介護保険のサービスの提供体制は定期的に見直され,言語聴覚士の対象および期待される役割に変化をもたらす。
「地域言語聴覚療法学」は2024年3月に厚生労働省から公布された言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令において,養成教育の必修内容に加えられた。本書はその地域言語聴覚療法学の理解を深めるためにまとめられた入門書である。執筆は,本シリーズのコンセプトである「初学者にわかりやすい書」を編纂するのにふさわしい「地域言語聴覚療法」に精通した言語聴覚士にお願いした。
第1章は,地域言語聴覚療法学を理解するうえで前提となる地域リハビリテーション等の基本的な考え方を簡潔にまとめている。第2章は,地域言語聴覚療法におけるサービスを提供する法的制度を網羅している。第3章は成人領域,第4章は主に小児領域における言語聴覚士の職務内容を整理し,ライフステージに従った情報収集,評価・訓練・指導,多職種連携など支援を概略し,その対象例を紹介した。
必修の教育内容に加わった「地域言語聴覚療法学」ではあるが,地域における言語聴覚療法は,実際には国家資格化以前から続く歴史がある。例えば,乳幼児健康診査やことばの教室,難聴幼児通園施設の取り組みはその代表例である。成人領域では,失語症友の会をはじめとする当事者会の支援は現在でもインフォーマルな支援として継続されている。地域言語聴覚療法は,地域の特性を生かし多職種協働のもと,その人らしい暮らしを支える専門的サービスとして,常に「最良の支援」とは何かを考える姿勢をもち続け,実践を重ねることで発展していくことが期待される。
本書が,地域における言語聴覚療法を学問的に学ぶ一助となることを期待している。
2024年12月
内山千鶴子・黒川容輔・黒羽真美
目 次
第1章 地域言語聴覚療法の基本概念
Ⅰ地域リハビリテーションの概要
Ⅱ地域言語聴覚療法とは
第2章 地域言語聴覚療法を支える制度
Ⅰ地域言語聴覚療法に関わる法制度
Ⅱ福祉制度の概要
Ⅲ発達・教育関連制度の概要
Ⅳ医療保険制度
Ⅴ介護保険制度
Ⅵインフォーマル支援
第3章 成人期の地域言語聴覚療法の展開
Ⅰライフステージに応じた言語聴覚士のかかわり
Ⅱ地域支援体制づくりへの参画
第4章 小児の地域言語聴覚療法の展開
Ⅰ妊娠から乳児期
Ⅱ幼児期
Ⅲ学童期
Ⅳ青年期・成人期
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup

言語発達障害
定型的な言語発達の経過,各言語発達障害を詳説。検査・指導・支援・評価・多職種連携等について,図表やイラストも使用し具体的にわかりやすく解説した。小児領域での需要が増す言語聴覚士の必携書。
-
-
-
pickup
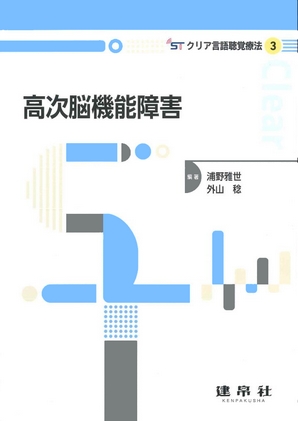
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは何か,障害における様々な症状の特徴,原因となり得る病変,評価法等に加え,リハビリテーションについても言及。言語聴覚士を目指す学生に最適な高次脳機能障害の入門書。
-
-
-
pickup
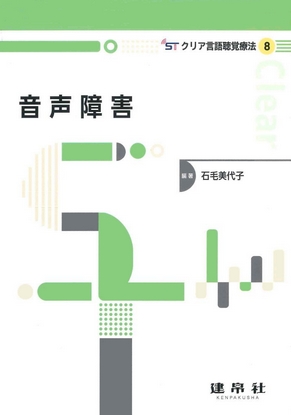
音声障害
音声障害の基礎知識,臨床(言語聴覚士の役割,検査,治療),専門性を要する特殊な病態の対応まで網羅した入門書。さらに新しい音声治療を含めた最新情報も盛り込み,臨床の場でも役立つ一冊にまとめた。
-
-
-
pickup

聴覚障害
聴覚領域に必要な検査,難聴児療育対応,補聴器フィッティング,人工内耳マッピング,中途失聴への支援,高齢難聴者への補聴・聴覚リハなどの技能習得のための入門書。具体例,図表やイラスト多用で明瞭。
-
-
-
pickup
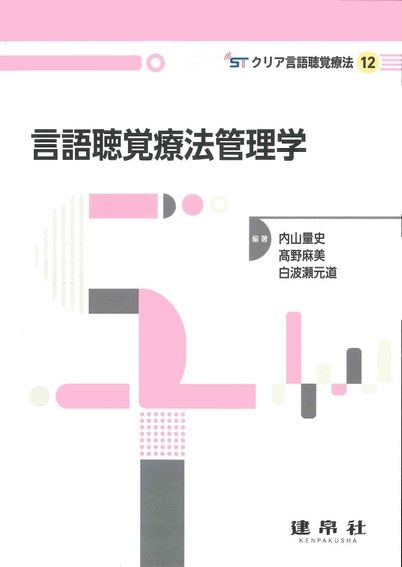
言語聴覚療法管理学
待望の「言語聴覚療法管理学」テキスト。現代の言語聴覚士に求められるマネジメントの視点から,現場で直面する様々な課題を体系的に学ぶ。多くの図表や側注を活用し,わかりやすく解説した入門書の決定版。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。