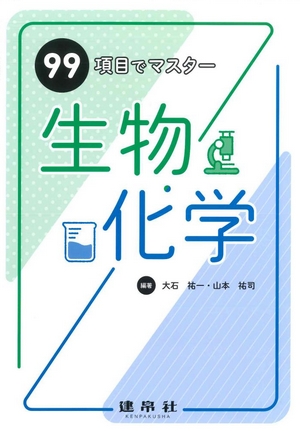令和7年9月1日
リメディアル教育用教科書の必要性
東京農業大学教授 大石祐一この著者の書いた書籍
筆者の所属する食品安全健康学科は,主に食品に関する学問を教育・研究する学科で,受験科目では理科を必須としている。生物,化学のどちらかを選択してもらうのだが,過半数が生物を選択して受験している。
しかし,当然のことながら食品学をはじめ,農学,栄養学,薬学,医学等,いわゆる理系とよばれる学系では生物学だけではなく,化学も非常に重要な科目である。また,このような学系では,生物学,化学をさらに応用させた,生物化学,分析化学,食品化学といった「〇〇化学」という科目が多く存在する。化学名と化学式,モル濃度の計算,希釈等といった化学の受験勉強をせずに入学した学生にとっては,化学系の科目の履修は特に大変苦労しているように思われる。他大学でも同様のことがあるのではないだろうか。
例えば,高校教育では理科を履修する際,一般的には基礎4科目である「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」のうち3科目を全生徒が履修することになっている。多くの高校では「基礎」とつく3科目は1,2年生で学び,その先の理科は,理系の大学に進みたい生徒が4四科目のうち1科目ないし2科目選択し修得するが,1科目しか選択肢がないところも少なくない。このような状況で,高校3年生の1年間で化学,生物,あるいは両方を十分に学ぶ機会が減ってしまっていることも考えられる。
現在,東京農業大学では入学後に学力試験を行い,成績によりこれらのリメディアル教育を実施している。とはいえ,該当科目の学生の理解度はまちまちで,担当教員も大変な思いをしている。さらに,リメディアル教育の履修後でも,入学時と同じレベルのままという学生も多々みられる。
このような現況になっている原因には,リメディアル用,つまり大学で必要とされる基礎学力を補うための教科書が存在せず,大学の教養レベルの教科書や高校の参考書を使用して授業が行われていることがあるのではないだろうか。大学の教養レベルのものでは,最初から専門的になってしまい理解に苦しんだり,文系から来た学生には難しすぎたりする。一方,高校の参考書では情報量が多すぎて学生には何が必要かわかりづらい等,といったところだろうか。
そこで今回,このような悩みを解消すべく「99項目でマスター生物・化学」を建帛社より上梓した。
リメディアル教育とは将来に希望を抱いて入学した学生の大学における学びを深め,充実させるための橋渡しができる教育の一環であると考えている。その教育に求められる教科書は,大学での学びを前提とした,個人の自発的な学びの引き出し,わからない単元のみの学習等により,不得意を埋めていくようなものではないだろうか。特に,農学,栄養学,薬学,医学等でのリメディアル教育には,生物学,化学において,以上のようなことを可能にする教科書が求められいると感じている。専門知識をスムーズに学べるためにも,その教育にあった教科書を見出すことが必要と考える。
目 次
第122号令和7年9月1日
発行一覧
- 第122号令和7年9月1日
- 第121号令和7年1月1日
- 第120号令和6年9月1日
- 第119号令和6年1月1日
- 第118号令和5年9月1日
- 第117号令和5年1月1日
- 第116号令和4年9月1日
- 第115号令和4年1月1日
さらに過去の号を見る
- 第114号令和3年9月1日
- 第113号令和3年1月1日
- 第112号令和2年9月1日
- 第111号令和2年1月1日
- 第110号令和元年9月1日
- 第109号平成31年1月1日
- 第108号平成30年9月1日
- 第107号平成30年1月1日
- 第106号平成29年9月1日
- 第105号平成29年1月1日
- 第104号平成28年9月1日
- 第103号平成28年1月1日
- 第102号平成27年9月1日
- 第101号平成27年1月1日
- 第100号平成26年9月1日
- 第99号平成26年1月1日
- 第98号平成25年9月1日
- 第97号平成25年1月1日
- 第96号平成24年9月1日
- 第95号平成24年1月1日
- 第94号平成23年9月1日
- 第93号平成23年1月1日
- 第92号平成22年9月1日
- 第91号平成22年1月1日
- 第91号平成21年9月1日
- 第90号平成21年1月1日
- 第89号平成20年9月1日
- 第88号平成20年1月1日