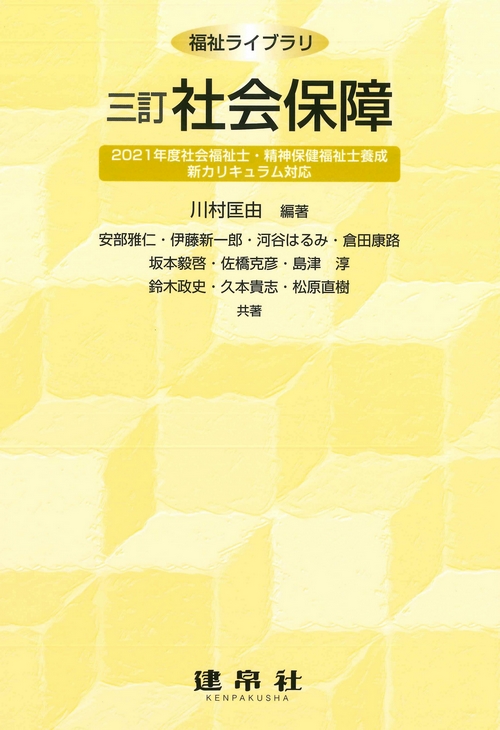内容紹介
まえがき
は し が き
周知のように,日本は第二次世界大戦(アジア太平洋戦争)で敗戦し,国内で約230万人,東アジアなど諸外国に同2,000万人もの犠牲者を出し,損害を与えたといわれている惨禍を反省し,これを教訓に,その後,今日まで官民一体となって軍事・戦争国家から平和・福祉国家への転換をめざし,政治や経済,社会の発展をはじめ,社会保障制度の整備・拡充に努めてきた。その結果,国際社会から奇跡ともいわれるほど短期間のうちに高度経済成長を遂げ,GDP(国内総生産)は近年,中国に追い抜かれたものの,アメリカ,中国に次いで世界第 3 位を占めるまでになった。
一方,国民の健康への関心の高さや食生活の改善,医療技術のレベルアップなども手伝い,平均寿命は飛躍的に延び,戦後間もないころ,50歳前後にとどまっていたものの,80歳から90歳へと延びて「人生100年時代」を迎え,日本国憲法により国民のだれもが基本的人権が尊重され,住み慣れた地域でいつまでも健康で文化的な最低限度の生存権が保障され,かつ安全・安心な生活を享受されるべく社会保障制度の一層の整備・拡充が求められている。
このようななか,長引くデフレ不況や経済のグローバル化,年金,医療,介護,子育て,生活保護などに対する国民の社会保障に対する関心は高まる一方だが,肝心の雇用・労働環境は国民の約 4 割が非正規雇用者に上っている。とくに国を支えるべき若者は一層の不安をつのらせており,ワーキングプアや“子どもの貧困”を招いている。
そこで,厚生労働省は2019(令和元)年 7 月,社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の受験資格に必要な現行の新カリキュラムを約12年ぶりに改定,2021(令和 3 )年 4 月の入学者より適用し,2024(令和 6 )年 2 月以降,この新々カリキュラムにもとづく国家試験を実施することになった。その共通基礎科目の一つが「社会保障」である。
幸い,2018(平成30)年 8 月に刊行した本書の初版は多くの大学などで教科書として採用され,版を重ねることになった。ついてはこれを機に,上述した新々カリキュラムにもとづく改訂版として内容を一新し,2021(令和 3 )年 4月以降の入学者にとって最適の教科書とすることにした。
ただし,内容は初版を踏襲し,終章を除く各章に実習対策をはじめ,レポート・卒論対策,受験対策,就活対策からなるコラムを設け,社会福祉士・精神保健福祉士の養成教育上,最善のテキストとなるよう,引き続き努めた。
幸いにもこのような編者の考えに対し,桜美林大学の島津淳および西南学院大学の倉田康路両先生をはじめ,全国の大学や短期大学で社会福祉士・精神保健福祉士の養成教育の一環として社会保障を第一線で教授されている各位より共著者として引き続きご協力をいただいた。その情熱に改めて敬意を表するとともに,出版の企画にご理解とご協力をいただいた株式会社建帛社に深く感謝したい。
2020(令和 2 )年 8 月
編者 川村 匡由
三訂にあたって
2019(令和元)年 7 月,社会福祉士・精神保健福祉士の養成教育の新カリキュラムの約12年ぶりの改定に伴い,2018(平成30)年 4 月,本書を上梓した。多くの大学などで教科書として採用され,2020(令和 2 )年 3 月には改訂版として刷新し,こちらも多くの学校で採用され,今般,その重版を迎えた。
しかし,この間,さらなる制度の見直しがあったほか,この新カリキュラムによる国家試験がいよいよ2024(令和 6 )年 2 月以降,毎年,実施されることになった。このため,この新たな国家試験に最新の制度を踏まえた内容で対応できるよう「三訂版」として刷新した。この三訂にあってもより多くの大学などで利用され,新たな社会福祉士・精神保健福祉士の養成および貴重なマンパワー(人材)として巣立ち,クライエントやその家族への支援にあたっていただければ幸いである。
2024(令和 6 )年 1 月
編者 川村 匡由
目 次
第1章 現代社会における社会保障制度の現状
1 人口動態の変化
2 経済環境の変化
3 労働環境の変化
第2章 社会保障の概念・理念と対象
1 社会保障の概念と範囲
2 社会保障の役割と機能
3 社会保障の理念
4 社会保障の対象
5 社会保障制度の展開
第3章 社会保障と財政
1 社会保障の財源と給付費(費用)
2 国民負担率
3 社会保障の財政問題と改革の方向
第4章 社会保険と社会扶助
1 社会保険の概念と範囲
2 社会扶助の概念と範囲
3 社会保険と社会扶助
第5章 公的保険制度と民間保険制度の関係
1 保険の機能と構造
2 民間保険
3 公的保険(社会保険)制度と民間保険制度
第6章 社会保障制度の体系
1 医療保険制度
2 介護保険制度
3 年金保険制度
4 労災保険制度と雇用保険制度
5 生活保護制度
6 社会手当制度
7 社会福祉制度
第7章 諸外国における社会保障制度
1 北欧―スウェーデン
2 西欧―イギリス・ドイツ・フランス
3 北米―アメリカ合衆国
4 オセアニア―オーストラリア
5 中国,ロシア,韓国
終 章 社会保障の課題
1 社会福祉の上位概念化
2 消費者福祉の視点
3 国際社会保障への地平
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup
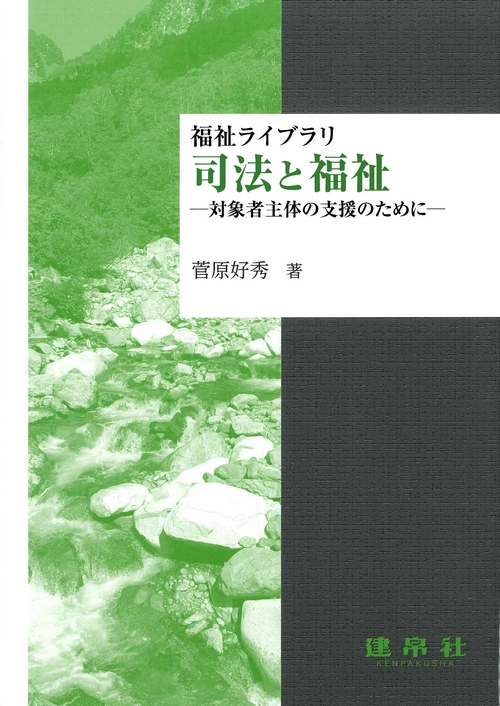
司法と福祉
再犯防止と生活支援という,司法と福祉の異なる見方を組み合わせた対象者支援のために,必要となる法的知識を判例を引きつつ解説。
-
-
-
pickup
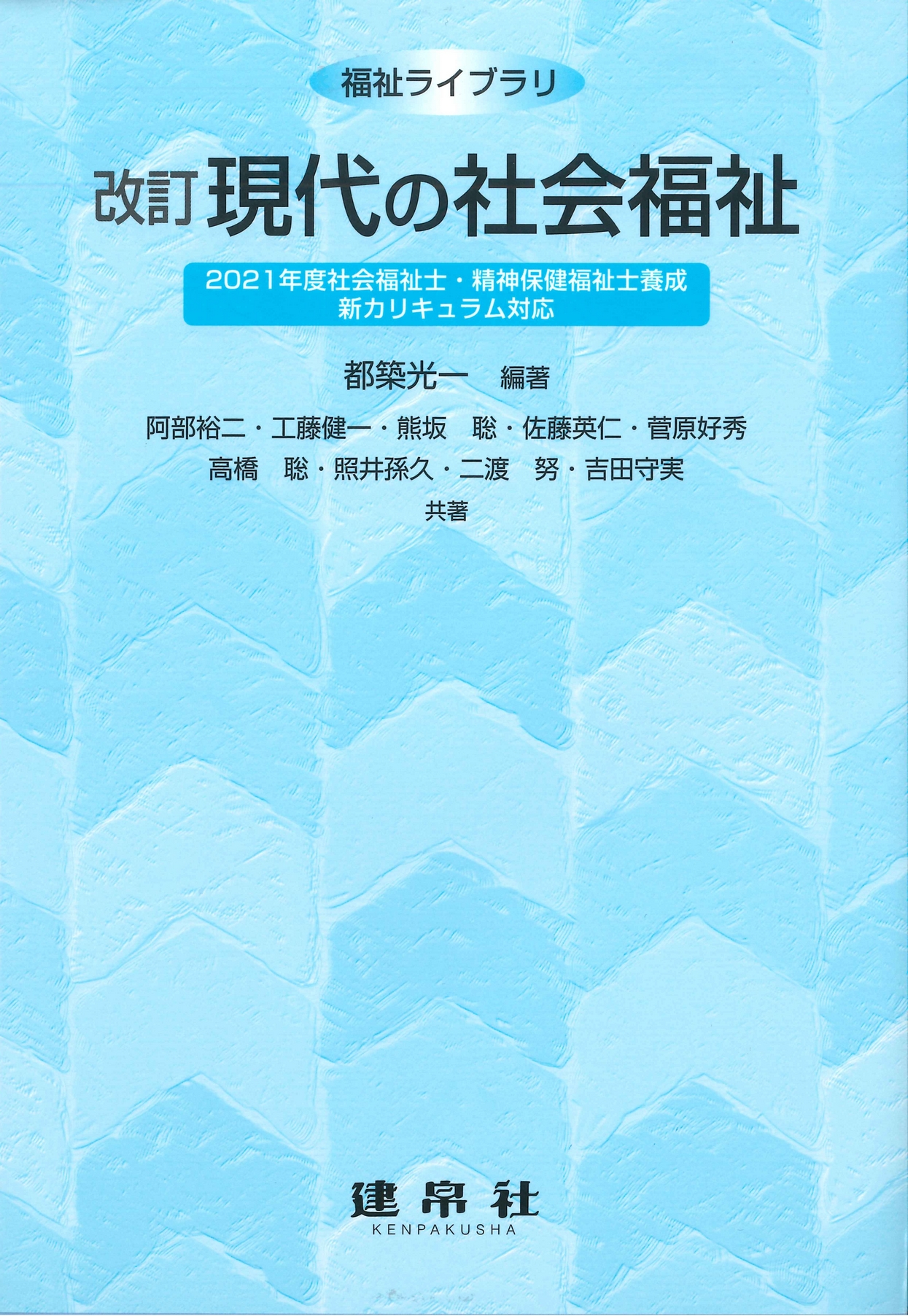
改訂 現代の社会福祉
2021年度より実施の社会福祉士養成課程「社会福祉の原理と政策」のテキスト。最新の法改正に対応し,今後の社会福祉の方向性に言及した。
-
-
-
pickup
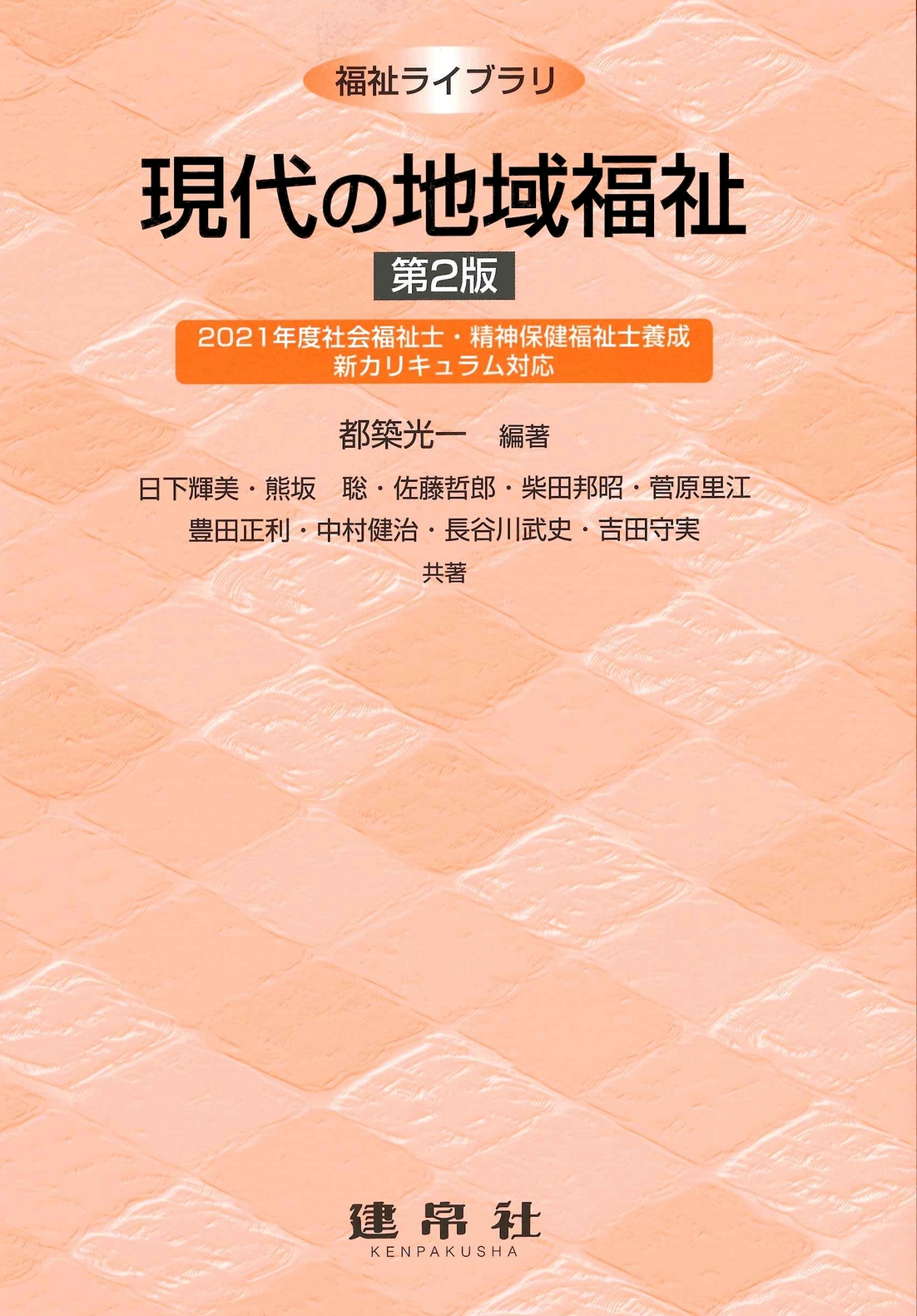
現代の地域福祉 第2版
2021年度より実施の社会福祉士養成課程における「地域福祉と包括的支援体制」に対応。地域の実情に合わせて加筆・調整を加えた第2版。
-
-
-
pickup
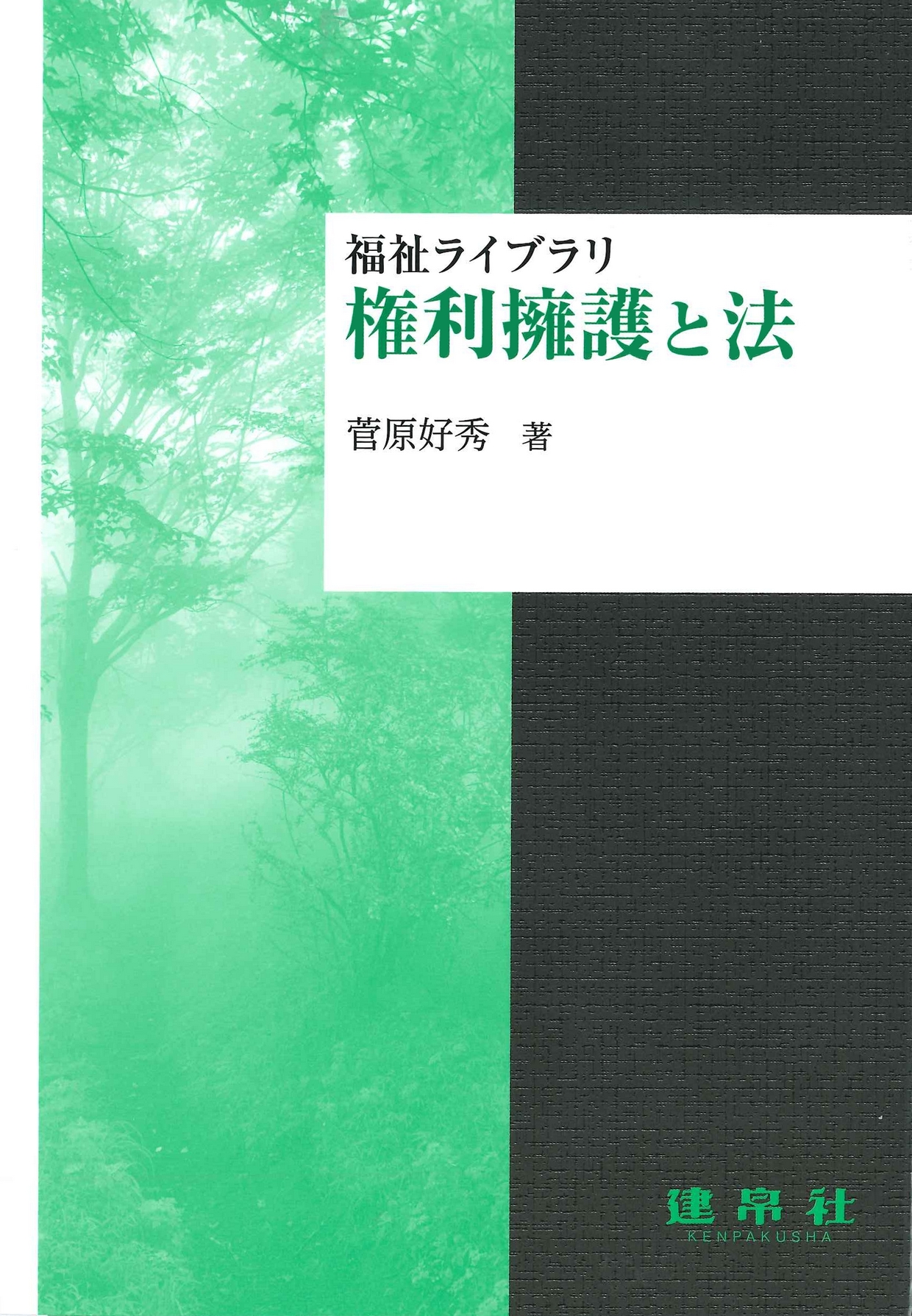
権利擁護と法
2021年度より実施の社会福祉士および精神保健福祉士養成課程「権利擁護を支える法制度」の教科書。事例問題を含む過去問解説や実際の判例を通じ,法を駆使した意思決定支援を実践的に学べるよう編集。
-
-
-
pickup
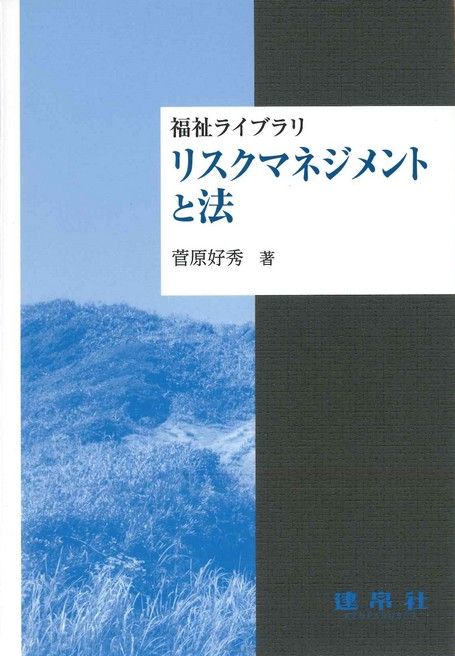
リスクマネジメントと法
介護,医療,保育,学校等の現場における事故と訴訟。判例を通じ,法的な視点からそうした現場でのリスクマネジメントについて詳述。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。