保育士養成課程「子ども家庭福祉」に対応した教科書。 子ども家庭福祉の理念と概要を述べ,現代における子どもの問題と病理を具体的に検討,子ども家庭福祉の制度と歴史を学ぶ。 また,将来の子ども家庭福祉と子どもを取り巻く社会環境を,コラムや演習を通して実践的に学ぶ。
最新の動向に対応した四訂版。
保育士養成課程「子ども家庭福祉」に対応した教科書。 子ども家庭福祉の理念と概要を述べ,現代における子どもの問題と病理を具体的に検討,子ども家庭福祉の制度と歴史を学ぶ。 また,将来の子ども家庭福祉と子どもを取り巻く社会環境を,コラムや演習を通して実践的に学ぶ。
最新の動向に対応した四訂版。
2016(平成28)年6月3日,「児童福祉法」が改正された。最も大きな改正点は,児童福祉の理念である。第1条では,「全て児童は,児童の権利に関する条約の精神にのつとり,適切に養育されること,その生活を保障されること,愛され,保護されること,その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」とし,子どもの福祉が“welfare”から“well-being”に代わった。この「児童福祉法」の改正が「保育所保育指針」の改定につながり,2018(平成30)年4月1日から適用された。
「保育所保育指針」の改定の方向性は,(1)乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実,(2)保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ,(3)子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直し,(4)保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性,(5)職員の資質・専門性の向上である。
さらに近年の児童を取り巻くさまざまな要因は,「子どもの権利条約」に示されている児童の最善の利益に反するような状況,たとえば児童虐待やその他の社会的養護を必要とする児童の増加等(本文に詳述)が多々あり,それが「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」の改正につながっていると思われる。
この改正により,2019年度から保育士養成課程の教科目および教授内容も改められ,「児童家庭福祉」の科目は「子ども家庭福祉」として名称と教授内容が一部変更されている。大きな変更点としては,「子どもの人権擁護」という大項目が新たに設けられたことであるが,その他にも,地域における子育て支援の重要性や,貧困家庭・外国にルーツをもつ子どもとその家庭に関する内容なども新たに反映されることとなった。
本書は,これらの法律等の改正,科目の教授内容に沿いながら,養成課程で学ぶ学生が理解しやすく,同時に,問題意識をもって日々の研鑽を積むことができるよう,できるだけ平易な文章を心がけ,また,学生の主体的な学びを図るために演習コーナーを設けた。
多様化する保育ニーズ・虐待・待機児童の問題等,児童を取り巻く環境はさまざまである。これらの問題は一朝一夕に解決することは困難であるが,保育者を志す学生の意識が変わり,これからの保育や養護を担っていくことになれば早期に解決の方向が見えてくると思う。
本書を大いに活用し,現代社会における子どもたちの実態を学び,自分たちは今何をすべきかを学び取ってほしい。
2020年2月
著者を代表して 松本峰雄
第1章 子ども家庭福祉とは
1 子ども家庭福祉の概念と理念
2 子どもの人権擁護と子ども家庭福祉の理念
3 子どもの福祉の本質
第2章 子ども家庭福祉の概況
1 現代社会と子ども家庭福祉
2 次世代育成支援と子ども家庭福祉
3 社会的養護の概況
4 母子保健
5 子どもの健全育成
第3章 多様な保育ニーズと保育問題
1 保育所の現状
2 多様な保育ニーズ
3 待機児童
4 認定こども園
5 ひとり親家庭
6 少子化と地域子育て支援(子ども・子育て支援新制度)
7 貧困家庭と外国にルーツをもつ子どもとその家庭
第4章 子どもの養護問題と虐待防止
1 子どもの養護問題
2 子ども虐待
3 DVとその防止
第5章 障害のある子どもの問題
1 保育者が障害についてなぜ学ぶ必要があるのか
2 障害について
3 障害のある子どもの状況について
4 障害のある子どもへの施策と福祉サービス
5 より充実した福祉サービスに向けた法改正
6 障害のある子どもと家庭への支援について
第6章 子どもの行動に関する問題
1 子どもの行動
2 心理的な問題への対応
3 少年非行への対応
4 不登校,ひきこもり,ニートへの対応
第7章 子ども家庭福祉の歴史
1 欧米の子ども家庭福祉の歴史
2 日本の子ども家庭福祉の歴史
3 子どもの権利に関する歴史~国境を越えて~
第8章 子ども家庭福祉の制度と法体系
1 子ども家庭福祉に関する法体系
2 子ども家庭福祉に関する法律
第9章 子ども家庭福祉の実施体系と実施期間
1 子ども家庭福祉の実施体系
2 子ども家庭福祉に関する審議機関
3 子ども家庭福祉の実施期間
第10章 児童福祉施設
1 「児童福祉法」に規定されている施設
2 「児童福祉法」に規定されている事業
3 児童福祉施設等の運営
第11章 世界の子ども家庭福祉
1 先進各国の子ども家庭福祉
2 発展途上国の現状
第12章 子ども家庭福祉の専門職
1 子ども家庭福祉の範囲
2 専門職の種類(資格・任用資格・職名)
3 児童福祉施設や相談機関の専門職(資格)
4 その他の子ども家庭福祉関係者(資格)
第13章 子ども家庭福祉の方法論
1 子ども家庭福祉のサービスの特徴
2 子ども家庭福祉の専門技術
3 求められる倫理観
第14章 子ども家庭福祉サービスにおける専門機関との連携
1 連携の重要性
2 地域における連携・協働
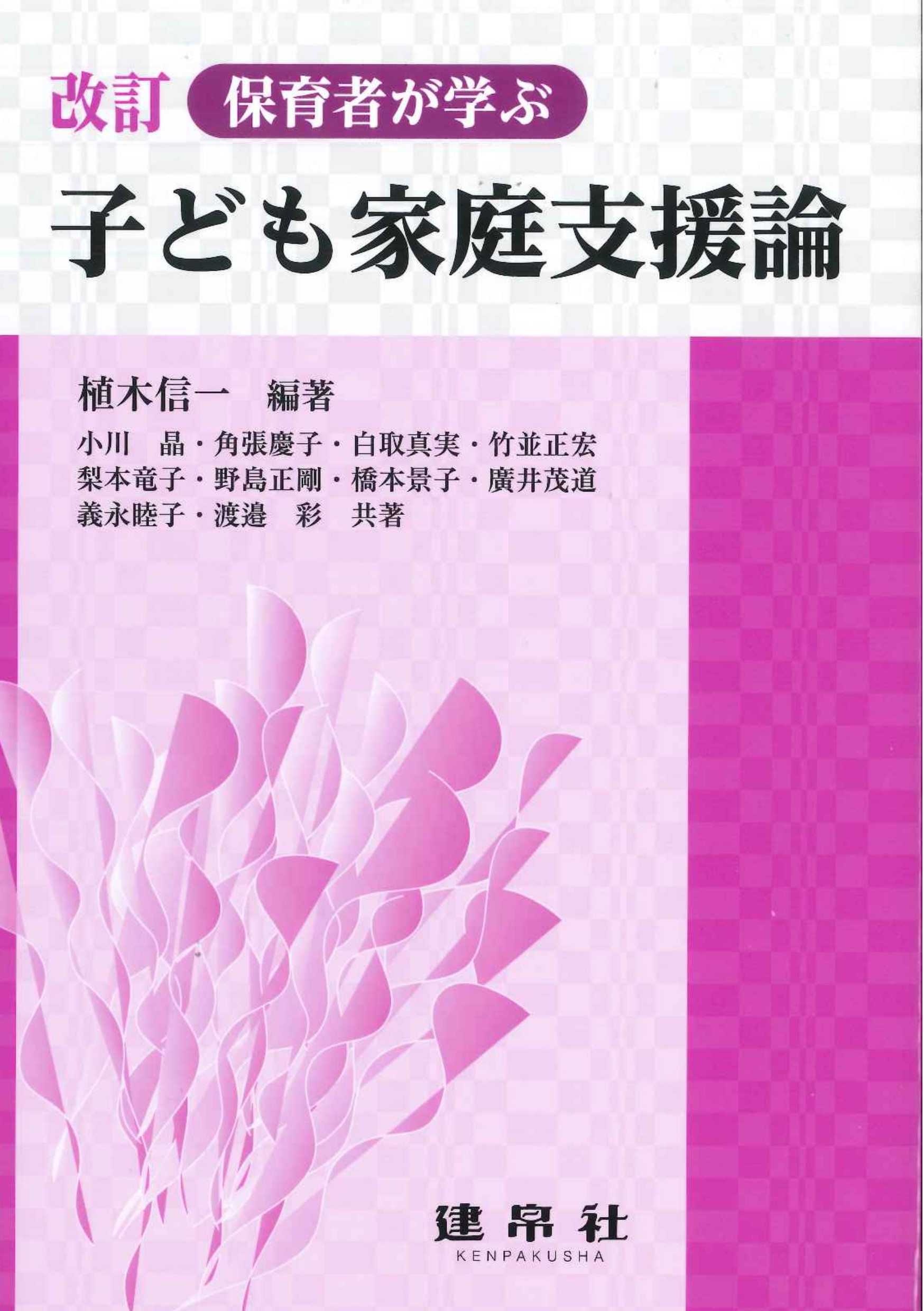
保育士養成課程における「子ども家庭支援論」に対応するテキスト。子どもとその家庭への支援についての知識を学ぶだけでなく,巻末の事例編を用い,演習的な学習も可能。法制度の改正に伴う改訂版。
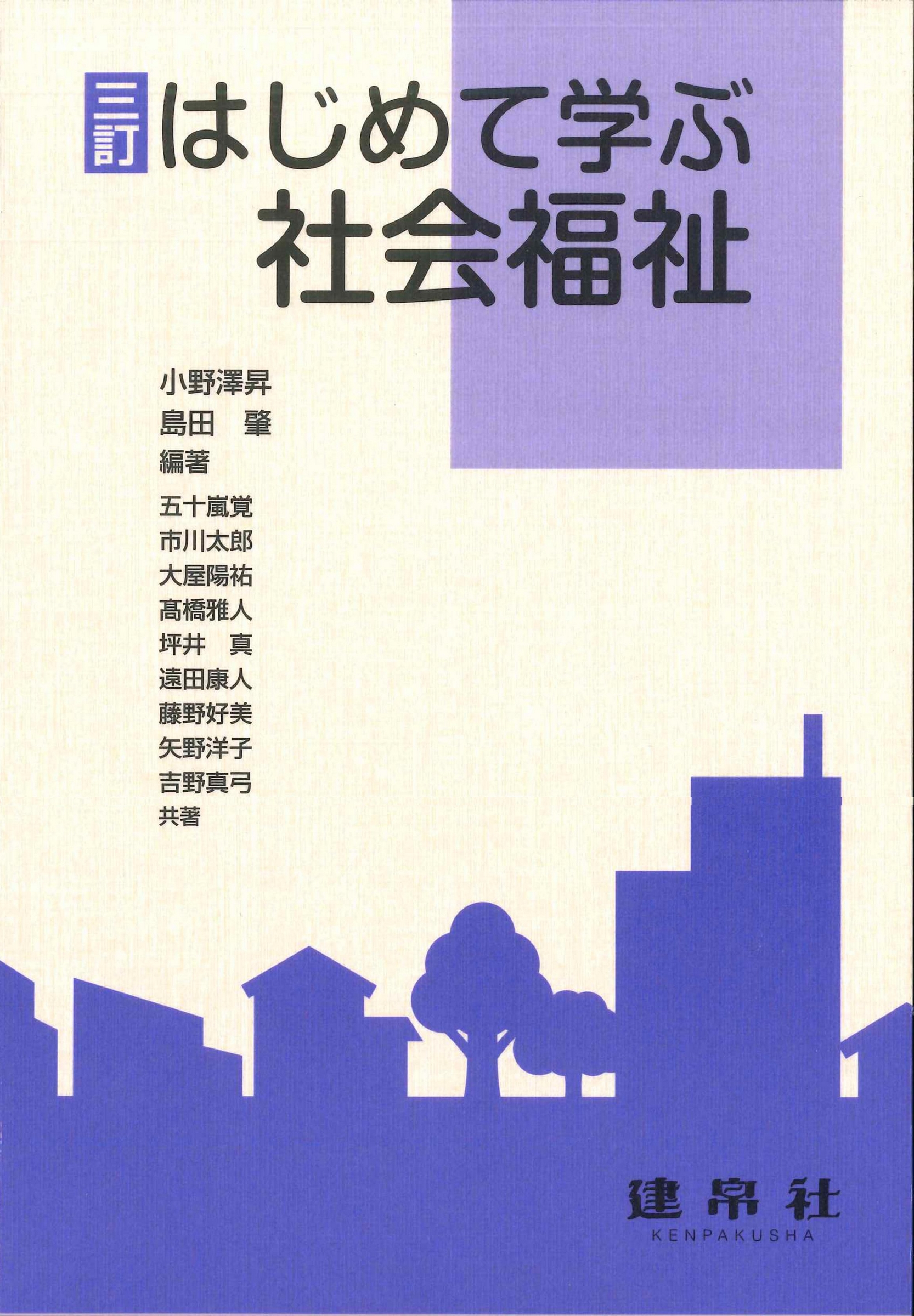
各章に「アウトライン」の頁を設け,初学者が要点を把握して概要を俯瞰しながら学習できる社会福祉の入門書。社会福祉における各分野の実態や今日的な課題・動向,最新の統計や法改正等を踏まえた三訂版。
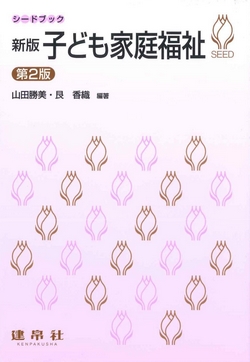
保育士養成課程,社会福祉士養成課程ほかの「子ども家庭福祉」(児童福祉論)に対応した教科書。子どもの人権を基盤に据えて,子どもの問題の背後にある社会の問題を意識して論ずる。
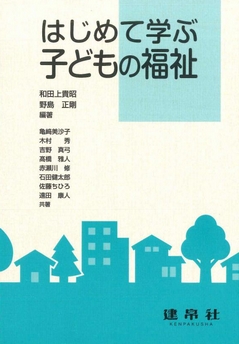
各章に「アウトライン」の頁を設け,初学者が要点を把握して概要を俯瞰しながら学習できる,子ども家庭福祉の入門書。今日的な課題・動向をふまえ,前身である『子どもの福祉』からリニューアルを図った。
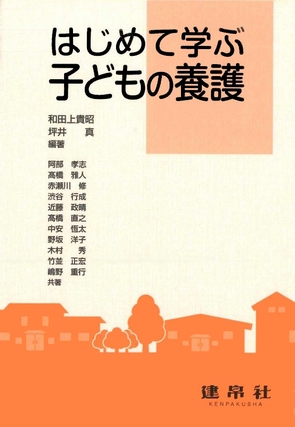
各章に「アウトライン」の頁を設け,初学者が要点を把握して概要を俯瞰しながら学習できる,「社会的養護Ⅰ・Ⅱ」のテキスト。最新の動向をふまえ,前身である『子どもの養護』からリニューアルを図った。
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。