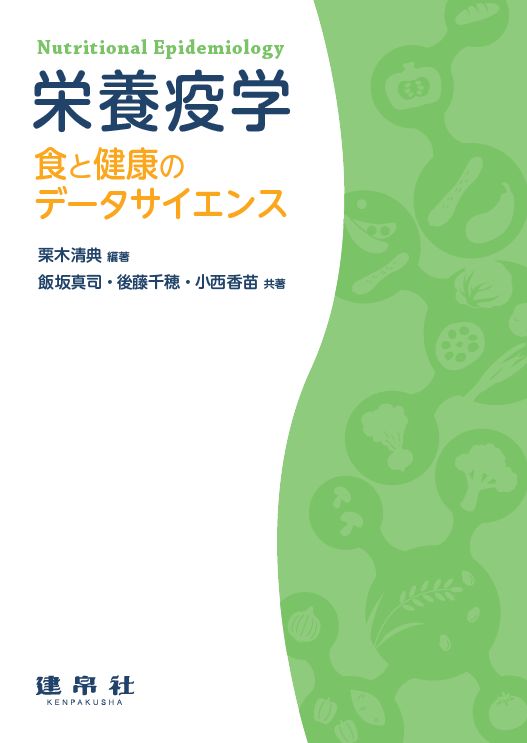令和7年9月1日
「栄養疫学×データサイエンス」教育の挑戦
静岡県立大学教授 栗木清典この著者の書いた書籍
政府の「AI戦略2019」に基づき,文部科学省は「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の整備を進めてきました。折しも,2020年初頭からのCOVID-19パンデミックは,日本社会のデジタル化の遅れを浮き彫りにし,教育分野におけるAI活用の立ち遅れへの危機感を社会全体に広げるきっかけとなりました。
2021年度より,すべての大学生等が数理・データサイエンス・AIの基礎を学ぶ,リテラシー教育が開始されました。さらに約半数の学生等が,専門分野の実践的な応用基礎力を修得する教育も始まりました。内閣府の「Society 5.0」では,AIによるビッグデータの解析を通じて新たな価値やサービスを創出し,社会課題の解決を図ることが求められています。この教育プログラムで育成された人材が,人間中心の社会において,AIによるビッグデータの解析を適切に科学的に理解して解釈したうえで,現実の課題に挑むことが期待されています。
特に「食と健康」分野において,データサイエンス・AIの活用は重要性を増しています。栄養疫学とは,人間集団を対象に健康や疾病と栄養との関係を明らかにし,有効な対策を講ずることに役立てるための科学です。健やかな食生活の提案や,生活習慣病,認知症,フレイル等の予防・改善を目指す管理栄養士をはじめとする食育・保健・医療・介護の専門家,それらの専門分野を学ぶ学生には,栄養疫学とデータサイエンス・AIを連携して学び,エビデンスに基づいた質の高い医療(Evidence-Based Medicine;EBM)・栄養学(Evidence-Based Nutrition;EBN)のサービス(教育を含む)を提供することが求められています。
しかし,食事調査が他の生活習慣の調査よりも曖昧で科学的厳密性に欠けるとみなされ,長らく栄養疫学の教科書は執筆されませんでした。このような中で,初学者にもわかりやすい『栄養疫学 ~食と健康のデータサイエンス~』を建帛社より上梓しました。「Society 5.0の栄養疫学」を志す学生や各分野の専門家に向け,EBM・EBNとデータサイエンス・AIの接点をわかりやすく解説しています。食品開発に携わる研究者にとっても,機能性表示食品の開発などに役立つ内容となっています。
栄養疫学を学ぶにあたって,「なぜ?」を問う疫学的思考と,「どうやって?」を実装するデータサイエンス・AIの技術の両面をバランスよく学ぶ機会を提供します。因果推論の難しさやAIモデルの限界を理解する過程は決して容易ではありません。しかし,異なる学問を横断的に学ぶことで,より強力な問題解決力を身につけられる実感を得るはずです。専門性を深めながら新しい技術にも対応できるという自信は,将来への希望となり,学習へのモチベーションを高めてくれます。
栄養疫学とデータサイエンス・AIの融合は,個人の健康支援にとどまらず,公衆衛生や地球規模の食料問題にも貢献し得る可能性を秘めています。学生や各分野の専門家がこの2つの学問を武器に,「食と健康」の未来を担うリーダーへと成長することを心から期待しています。
目 次
第122号令和7年9月1日
発行一覧
- 第122号令和7年9月1日
- 第121号令和7年1月1日
- 第120号令和6年9月1日
- 第119号令和6年1月1日
- 第118号令和5年9月1日
- 第117号令和5年1月1日
- 第116号令和4年9月1日
- 第115号令和4年1月1日
さらに過去の号を見る
- 第114号令和3年9月1日
- 第113号令和3年1月1日
- 第112号令和2年9月1日
- 第111号令和2年1月1日
- 第110号令和元年9月1日
- 第109号平成31年1月1日
- 第108号平成30年9月1日
- 第107号平成30年1月1日
- 第106号平成29年9月1日
- 第105号平成29年1月1日
- 第104号平成28年9月1日
- 第103号平成28年1月1日
- 第102号平成27年9月1日
- 第101号平成27年1月1日
- 第100号平成26年9月1日
- 第99号平成26年1月1日
- 第98号平成25年9月1日
- 第97号平成25年1月1日
- 第96号平成24年9月1日
- 第95号平成24年1月1日
- 第94号平成23年9月1日
- 第93号平成23年1月1日
- 第92号平成22年9月1日
- 第91号平成22年1月1日
- 第91号平成21年9月1日
- 第90号平成21年1月1日
- 第89号平成20年9月1日
- 第88号平成20年1月1日