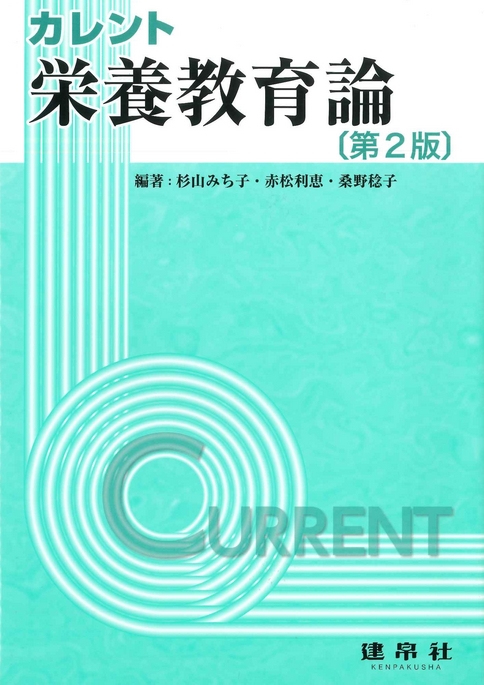栄養教育の理論とモデルを概観し,事例編により栄養教育の実践を深く理解できるように編集。ガイドライン改定に対応のほか,退院がん患者への栄養指導と市役所による食環境整備の事例を追加した第2版。
内容紹介
まえがき
はじめに
わが国は,世界に類を見ない超高齢社会に対応するために,地域包括ケアシステムの推進,急性期病院の病床数の削減と機能の転換,医療・介護連携の強化,在宅サービスの重視など保健医療福祉制度の急速な変革が推進されてきています。
国民の健康寿命を延伸し,医療・介護サービスを効率化するという観点から,1997年に厚生労働省「21世紀の管理栄養士のあり方検討会」において,管理栄養士による傷病者の栄養管理とチーム医療への参画が提唱されました。栄養士法の改定によって,管理栄養士の業務は,従来の「栄養の指導」から「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」となりました。2002年新カリキュラム改定によって,『栄養教育』には,体系的な行動変容理論・モデル,カウンセリング技法やPDCAサイクルによるマネジメントが導入されました。
さらに,近年の医療・介護保険制度改定においては,管理栄養士による栄養教育・栄養相談には退院支援や在宅訪問の取り組みの充実が求められてきました。さらに,地域包括ケアシステムの推進にあたって,地域の食環境の整備や住民参加型の地域社会づくりの観点が重視されてきています。
このような社会的ニーズに対応するために,『カレント栄養教育論』の編集にあたっては,平成27年4月の国家試験ガイドラインを踏まえたうえで構成しました。第Ⅰ編においては次の点に留意しました。
第1章 21 世紀の栄養教育を担う管理栄養士として理念を明確化すること。
第2章 栄養教育のための理論的基礎は簡潔な表現とし,抽象的な理論やモデルの理解やその活用を支援すること。
第3章 栄養教育のマネジメントは,その用語や方法を理解し,実践時に活用できること。
また,第Ⅱ編の栄養教育の実践事例では,様々な栄養教育の臨地における,比較的複雑な課題を有する事例(個別,集団)から,学生が教員とともにその特性や栄養教育の実際の取り組みについての理解を深め,考えていけることを重視しました。
本書の執筆は,栄養教育の専門家とこれからの栄養教育の教育研究を担う若手の研究・教育者に担当していただくことができました。また,第Ⅱ編の事例は,それぞれの栄養教育現場で活躍している管理栄養士が協力執筆することによって,栄養教育のリアルで生き生きとした取り組み事例(教科書用に作成編集されている)を提供することができました。これらの執筆者のご協力によって,本書は,現代社会の様々な栄養問題を解決するための栄養教育の基礎から実践的活用までを学べる新しい教科書となりました。
本書をご利用頂いた教員や学生の皆様は,是非,ご意見や,ご要望,ご感想をお寄せ下さいますようにお願いいたします。これからの栄養教育の学習の一助となるようにさらに改訂して参りますので,どうぞよろしくお願いいたします。
2016(平成28)年5月吉日
編者 杉山みち子
赤松 利恵
桑野 稔子
「第2版」にあたって
2016(平成28)年に初版を刊行して以来4年が経過し,その間,管理栄養士国家試験出題基準の改定がなされ,また診療報酬・介護報酬の改定においては,管理栄養士の専門業務に関わる報酬制度の見直しが行われました。さらに,地域包括ケアシステムは推進され,高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向けて管理栄養士業務はより一層の専門性を求められてきています。
今回,国家試験出題基準の改定に対応し,「ナッジ」「動機づけ面接」といった新たな項目について加筆しました。さらに,がん患者への栄養指導や公衆栄養分野でのポピュレーションアプローチの重要性が高まっていることも鑑み,事例編では栄養教育論としての切り口から,第9章(傷病者)に「胃がん患者の退院後の栄養食事指導」を,新章として「第12章 食環境の整備」を設け,「市内飲食店事業者等を巻き込んだ食環境整備の推進」の事例を加えました。どちらもその方面での実務経験をお持ちの先生方にご執筆いただきました。
ところで,この度のCOVID-19によって「New Normal」と言われ急激に変化していく社会や日常の生活様式において,今後の栄養教育学習において重視すべき理論,技術およびその実務のあり方も大きく変化していくことになります。そこで,本書をご活用いただく教員や学生の皆様には,今後の改訂にあたってのご意見を,是非,お寄せいただけますようにお願いいたします。
本改訂により,栄養教育学習の一助となれば幸いです。
2020(令和2)年6 月
編者
目 次
第Ⅰ編 栄養教育の理論
第1章 栄養教育の概念
1.栄養教育の目的・意義
2.栄養教育の対象と機会
第2章 栄養教育のための理論的基礎
1.栄養教育と行動科学
2.行動科学の理論とモデル
3.組織づくり,地域づくりへの展開
4.食環境づくりとの関連
5.栄養カウンセリング・コミュニケーション
第3章 栄養教育マネジメント
1.栄養教育マネジメント
2.健康・食物摂取に影響を及ぼす要因のアセスメント
3.栄養診断
4.栄養教育の目標設定と評価
5.栄養教育計画立案
6.栄養教育プログラムの実施
第Ⅱ編 栄養教育の展開の実際―ライフステージ・対象者別栄養教育の展開
第4章 妊娠・授乳期の栄養教育
1.妊娠・授乳期の栄養教育の留意事項
2.事例:妊娠期の外来・検査入院中の栄養教育
第5章 乳幼児期の栄養教育
1.乳幼児期の栄養教育の留意事項
2.事例:幼児期の偏食・小食への保護者への栄養教育
第6章 学童期・思春期の栄養教育
1.学童期・思春期の栄養教育の特徴と留意事項
2.教科における事例:小学校第6学年の食育の授業
3.事例:女子大学生の食行動を改善する栄養教育の試み
第7章 成人期の栄養教育
1.成人期の栄養教育の留意事項
2.事例:大学病院更年期外来における栄養教育
3.事例:生活習慣病の栄養教育(メタボリックシンドローム)
4.事例:壮年期女性の生活習慣病おいびメタボリックシンドローム予防の栄養教育
第8章 高齢期の栄養教育
1.高齢期の栄養教育の留意事項
2.事例:地域包括支援センターから依頼された後期高齢者の訪問栄養教育
3.事例:市町村における介護予防・栄養改善プログラム
第9章 傷病者の栄養教育
1.傷病者の栄養教育の留意事項
2.事例:慢性腎不全患者の外来栄養食事指導
3.事例:糖尿病(前期高齢者)の栄養食事指導
4.事例:脂質異常症を併発する肥満患者の個別・集団栄養教育
5.事例:胃癌患者の退院後の栄養食事指導
第10章 障がい者の栄養教育
1.障がい者の栄養教育の特徴と留意事項
2.事例:自閉症児の病院が依頼での個別栄養食事指導
3.事例:身体障がい児(脳性まひ)の個別栄養相談
4.事例:特別支援学校での栄養教育~栄養教諭と給食の役割
第11章 アスリートの栄養教育
1・アスリートの栄養教育の特徴と留意事項
2.事例:高校野球部のアスリートへの栄養サポートにおける栄養教育
第12章 食環境の整備
1.事例:市内飲食店事業者等を巻き込んだ食環境整備の推進
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup
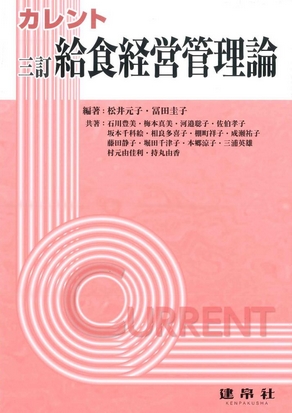
三訂 給食経営管理論
管理栄養士養成向け給食経営管理論の教科書。日本人の食事摂取基準(202年版)等,最新の情報に沿う。
-
-
-
pickup
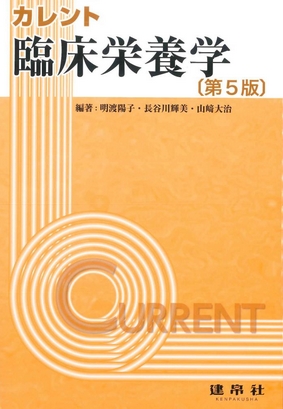
臨床栄養学 第5版
日本人の食事摂取基準(2025年版),脂質異常症,肥満症ほか,各疾患ガイドラインは最新動向に沿う。診療報酬・介護報酬も最新の内容で網羅。用語解説も充実。
-
-
-
pickup

改訂 公衆栄養学 第5版
医師ほか他職種や他分野からの管理栄養士の視点を取り入れるとともに,他教科とのつながりに配慮。公衆栄養プログラムの展開にかかわる部分に紙面を割く。最新の統計データに対応した改訂第5版。
-
-
-
pickup
-

三訂 社会・環境と健康:公衆衛生学 第2版
「社会・環境と健康」の範囲を網羅しつつコンパクトに収載。2023年改訂の管理栄養士国家試験出題基準に準拠し,国民健康・栄養調査および統計データ等を最新に更新した三訂第2版。
-
-
-
pickup
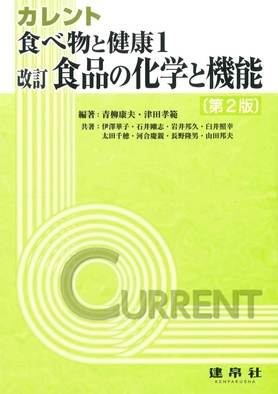
改訂 食べ物と健康1:食品の化学と機能 第2版
「食べ物と健康」領域のうち,食品の分類,機能と化学,表示と規格・基準を中心にまとめた。機能別に成分を理解し,食品の表示や規格まで順序よく学べる。成分表増補2023年版対応。法令・統計データ刷新。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。