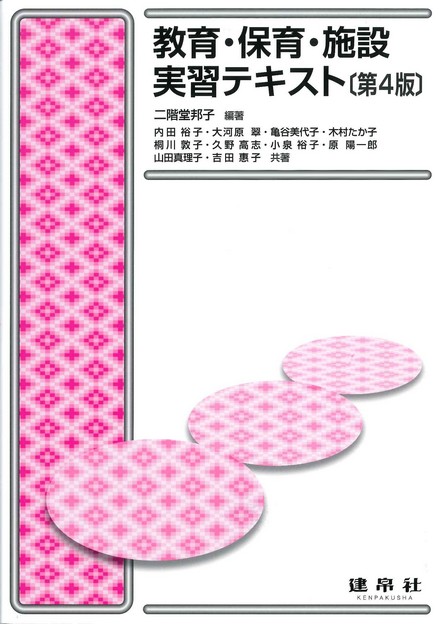内容紹介
実習の事前学習と実習先での学び,事後学習までを網羅する。総合学習にそなえて教材研究も掲載。
2017年告示の幼稚園教育要領,幼保連携型認定こども園教育・保育要領,保育所保育指針の対応と,その他法令,統計データを更新した第4版。
まえがき
はじめに
子どもは一冊の本である
その本から
われわれは何かを読み取り
その本に
われわれは何かを書き込んで
いかなければならぬ
ペーター・ローゼッカー
われわれ,すなわちあなたです。
今,子どもという一冊の本に出会おうとしています。
なぜこの養成校に入ったのですか。
どういう保育者になろうとしていますか。
きっと,あなたの意志は強く,希望に満ちていることと思います。
戦後,67 年が経ち,児童福祉法が改正され,平成 21(2009)年には新しい幼稚園教育要領,保育所保育指針が施行されました。その背景には,平成 18(2006)年に改正された教育基本法があります。その第 11 条に「幼児期の教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである」と新たに幼児期の教育が規定されました。
このような大きな教育の変革の中で子どもたちは生きています。平成 23(2011)年3月 11 日,東日本大震災,その後に続いて襲った津波,福島第一原発事故などは,戦後最悪の災害といわれています。その中,未来に夢をもって生きていく子どもたちのたくましく成長する姿を見守り,援助し,さらなる「生きる力」を育てていく我々の使命は,はかりしれません。そして,子どもたちを
取り巻く環境(物的・人的)に対する配慮も気づきもますます重要なものとなってきています。まさに専門職です。専門職となるための具体化と総合化が実習です。実習園では,未来の保育者を養成するために門戸を開けて待っています。その実習において学生の皆さんが困らないように,今回は新しく4名の執筆者が加わり「教育・保育・施設実習テキスト第2版」を作り上げました。
このテキストはあくまでも机上のものです。実習園で体験する子どもの言葉,表情,身振り,手振りから子どもの心を五感で読み取って,書き込みを入れてください。
実習を終えたとき,あなたと子どもに関する,あなただけの本が一冊できていることでしょう。
最後に,建帛社の松崎克行氏,宮﨑潤氏にお力添えをいただきましたことをお礼申し上げます。
2013 年1月
著 者 一 同
第4版にあたって
本書の初版発行より 10 年が経とうとしている。その間,児童福祉法等の改正や,子ども・子育て支援新システムの実施等に対応して,本書は 2013(平成 25)年に第2版,2016(平成 28)年に第3版を発行してきた。
そして,幼稚園教育要領,幼保連携型認定こども園教育・保育要領,保育所保育指針が 2017(平成 29)年3月に新たな形で告示されたことや,2019(平成 31)年度から新しい教職課程・保育士養成課程が施行されることを受け,その他の法令改正,統計データの更新も含めて,このたび本書を第4版として刊行した。
2019 年1月
著 者 一 同
目 次
第2章 実習の前に(心得/オリエンテーション/実習の内容と方法/指導計画の立て方/実習記録の書き方/子どもの理解)
第3章 実習先に行ってから(子ども・教職員とのかかわり/実習中の心構え/実習日誌/指導実践/指導実習後の反省)
第4章 実習の後に(実習における自己評価/実習園とのかかわり/養成校における学生指導と評価)
第5章 教材研究(7教材)
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup
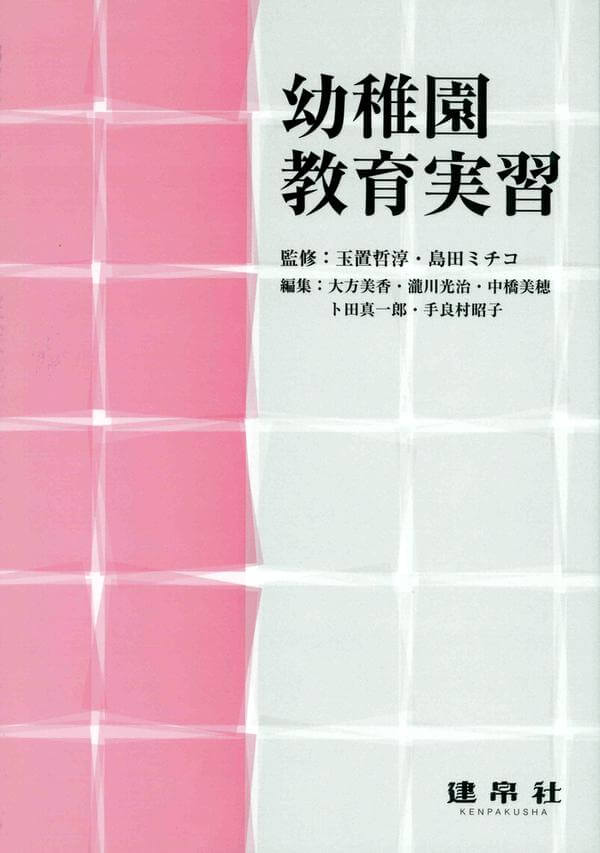
幼稚園教育実習
実習の準備段階から実習終了までの時系列をたどる形で章を構成し,各章の内容も実際に実習生が取り組む内容を時系列順で示す。「何を」「どのように」取り組めばよいのかを具体的に記述する。
-
-
-
pickup
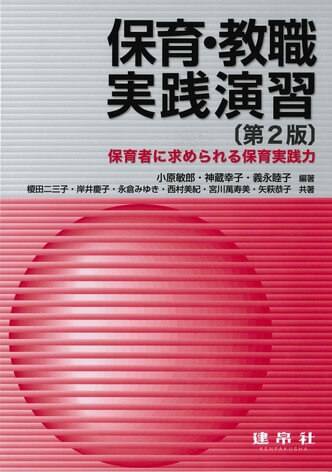
保育・教職実践演習 第2版
平成29年告示の保育所保育指針,幼稚園教育要領,幼保連携型認定こども園教育要領の改定(訂)対応したテキスト。理論編,方法・技法編,実践・演習編の3部構成で展開。
-
-
-
pickup
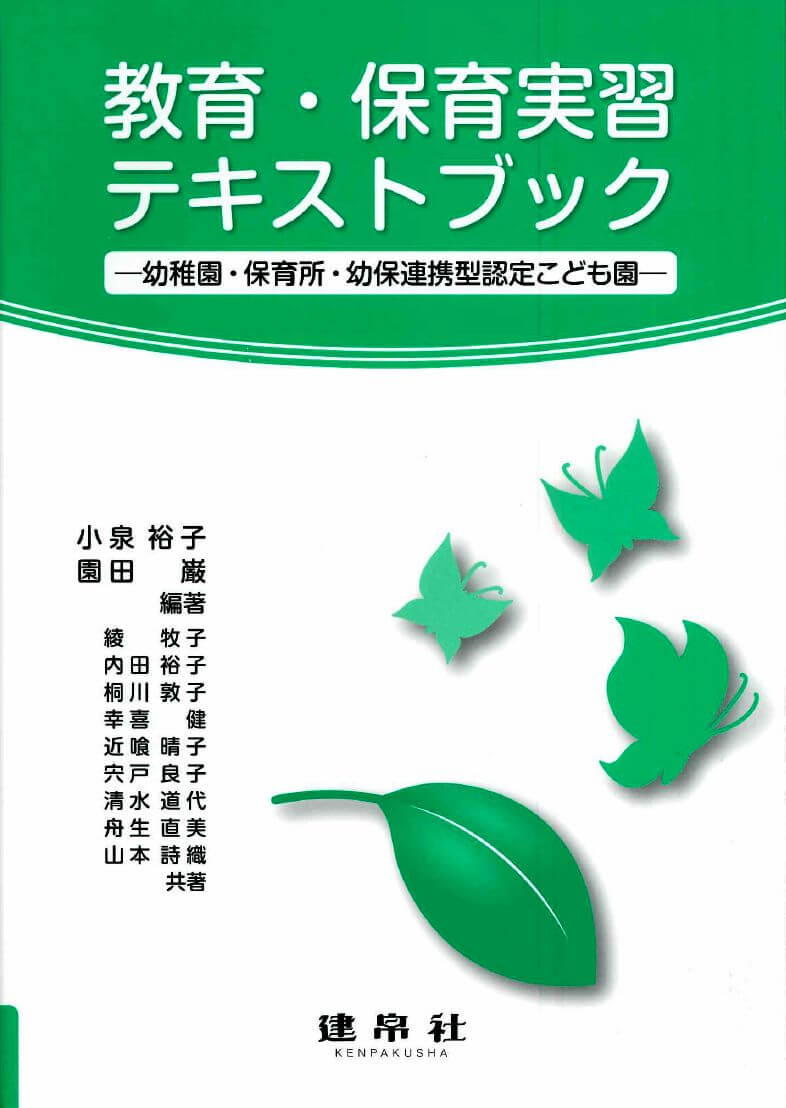
教育・保育実習テキストブック
専門性(保育力)を持った保育者を目指す実習生に養ってほしい力,「実習力」をテーマに,経験豊富な執筆陣が多様性のある事例を盛り込んで解りやすく記述。2019年度新保育士養成課程対応。
-
-
-
pickup
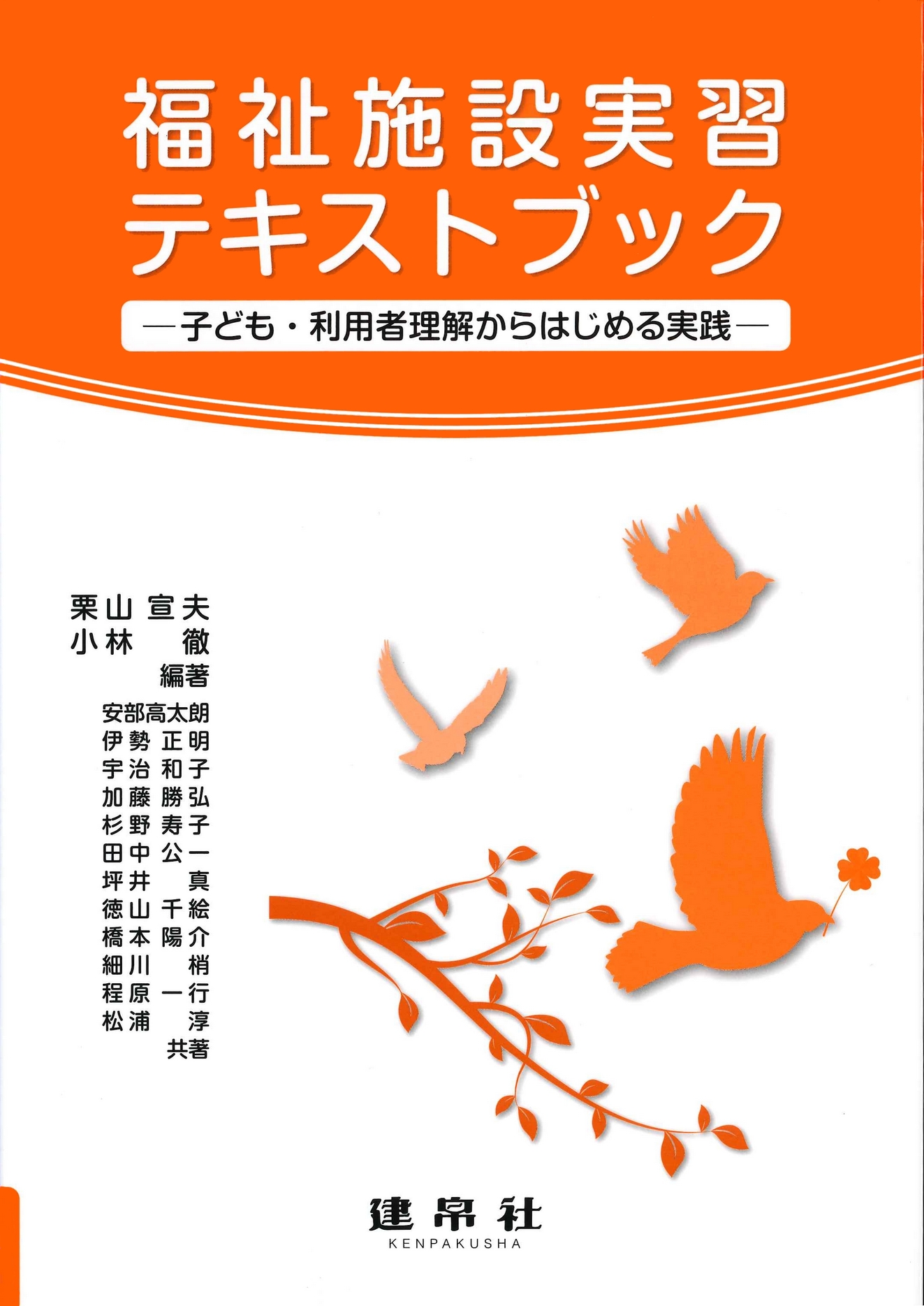
福祉施設実習テキストブック
保育実習(施設)に対応したテキスト。福祉施設の子ども・利用者の理解を念頭に置き,実習対象の全施設種別を網羅して丁寧に解説した。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。