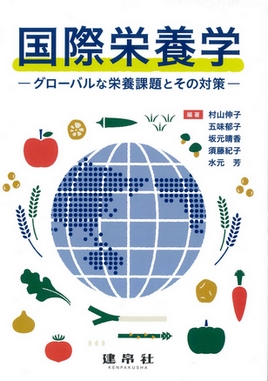『国際栄養学』は,現代における栄養や食生活に関する国際的な課題を多角的に取り扱い,その解決に向けて必要な知識とスキルを提供することを目的とした教科書である。特に日本を含む国際的な視点から栄養問題にアプローチし,現場から政策立案までの広範な視点を養うことを目指している。
世界の人口は現在81億人を超え,今後数十年にわたって増加が続く見込みであるが,この増加の大部分は中所得国や低所得国に集中している。このような状況において,世界の栄養問題は複雑化しており,食料不足や栄養不良だけでなく,過剰栄養や地球温暖化による環境負荷など,複数の課題が同時に進行している。2023年現在,7億3500万人が飢餓に直面しており,コロナウイルス感染症拡大前の2019年と比べて増加している。このような背景から,国際社会においては,食料安全保障や持続可能な食料システムの構築が急務となっている。
国際的な栄養問題に対する解決策は,個別の国や地域にとどまらず,世界全体で協力し合うことが求められる。1992年の世界栄養宣言では,「栄養的で安全な食物へのアクセスは個々人の権利である」と明言されており,これを実現するためには,各国が協力して政策を策定し,実践していくことが必要不可欠である。また,持続可能な開発目標(SDGs)の一環として,「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」という目標が掲げられており,これらを達成するために栄養・食生活が果たすべき役割は非常に大きい。
本書は,こうした国際的な課題に対応できる人材を育成するために執筆されたものである。具体的には,健康・栄養に関連する多様な課題を発見し,解決に向けた政策的な観点からのアプローチを学ぶことができる。また,国際的な文脈で活躍するために必要なリーダーシップやコミュニケーション能力,そして倫理観と使命感を養うことができるよう,専門的な知識と実践的なスキルを提供する内容となっている。
さらに,日本国内における栄養政策だけでなく,国際的な保健・栄養政策の立案と実践に役立つ内容を豊富に取り入れている。これにより,読者は,栄養に関する多様な課題に対して,グローバルな視点から適切に対応する能力を身につけることができる。管理栄養士や栄養士を目指す学生だけでなく,国際保健学を学ぶ学生や,実際に国際的な栄養問題に取り組んでいる専門家にとっても参考になる一冊。