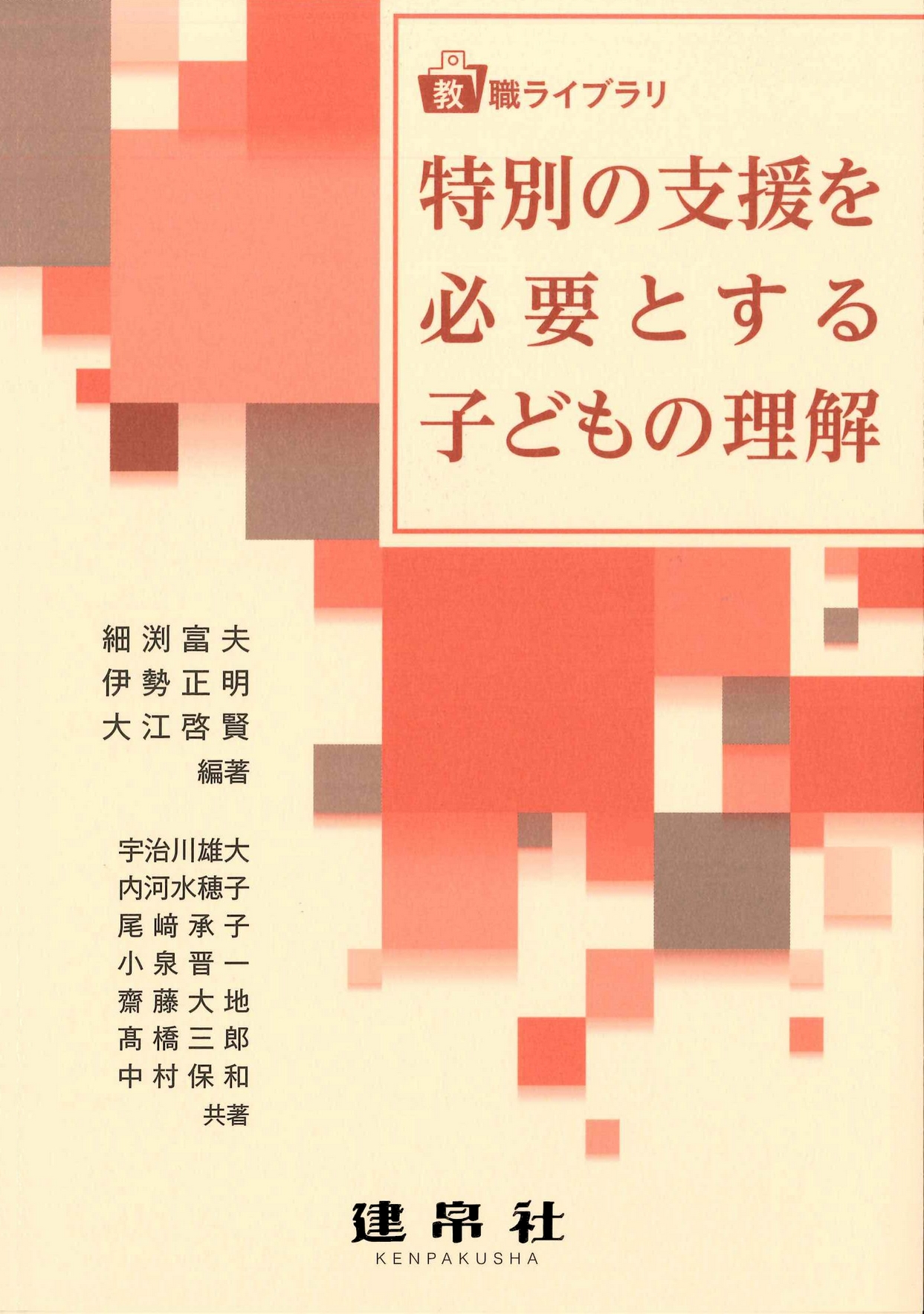教職課程の「特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する理解」に対応。各章の「事前学習」と「まとめ」により学びの確認を図る。
内容紹介
目 次
第1章 特別の支援を必要とする子どもを支える理念や教育制度
1 障害によらない特別な教育的ニーズへの注目
2 ICIDHのインパクトとICFへの展開
3 ノーマライゼーションの理念の発展と教育への影響
4 国内の教育制度の変遷と現在の課題
5 国内の障害児教育の制度と特別支援教育への展開
6 幼児期から思春期・青年期までの教育の枠組み
第2章 子どもの発達過程を理解するための基礎的な視点
1 発達の理解と発達保障
2 認知発達の理論
3 社会的発達の理論
4 道徳性発達の理論
5 各理論の一体的な理解
第3章 指導・援助方法のための基本的な視点
1 就学前の保育内容と就学後の教科指導の関係
2 TEACCHの哲学
3 応用行動分析におけるABC分析
4 カウンセリングの基礎と支援場面への適用
5 相談援助の基本と指導場面への援用
第4章 身体の不自由さから生じる困難の理解
1 視覚障害の理解と指導・援助
2 聴覚障害の理解と指導・援助
3 肢体不自由の理解と指導・援助
第5章 認知能力の低さや偏りから生じる困難の理解
1 知的障害の理解と指導・援助
2 ASD(自閉スペクトラム症)の理解と指導・援助
3 ADHD(注意欠如多動症)の理解と指導・援助
4 SLD(限局性学習症)の理解と指導・援助
5 知的障害・発達障害と関連する事項
第6章 病気や複合的な理由による困難の理解
1 病弱・身体虚弱の理解と指導・援助
2 医療的ケアの理解と指導・援助
3 重度重複障害(重症心身障害)の理解と指導・援助
4 重度重複障害(盲ろう)の理解と指導・援助
5 言語障害の理解と指導・援助
6 吃音の理解と指導・援助
7 情緒障害の理解と指導・援助
第7章 環境の制約により生じる困難の理解
1 日本語指導が必要な子どもの理解と指導・援助
2 貧困家庭の子どもの理解と指導・援助
3 被虐待児の理解と指導・援助
4 不登校の理解と指導・援助
第8章 特別の支援を組み立てるための枠組み
1 通常の学級で特別の支援を提供する形態・方法
2 通級による指導
3 交流及び共同学習
4 特別支援学級における自立活動
5 自立活動を意識した通常学級での指導の工夫
第9章 特別の支援を組み立てるための具体的な方法
1 個別の教育支援計画と個別の指導計画
2 合理的配慮に基づいた計画の立案
3 「発達の最近接領域」や「芽生え反応」の把握
4 ABC分析による問題事象の時系列整理
5 接続・連携のための共通言語
第10章 特別支援教育コーディネーターの業務と役割
1 特別支援教育コーディネーターの役割と位置づけ
2 「連携と協働」の意味と相談援助技術
3 保護者との連携
4 校内の教職員との連携
5 校外の専門職との連携
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup
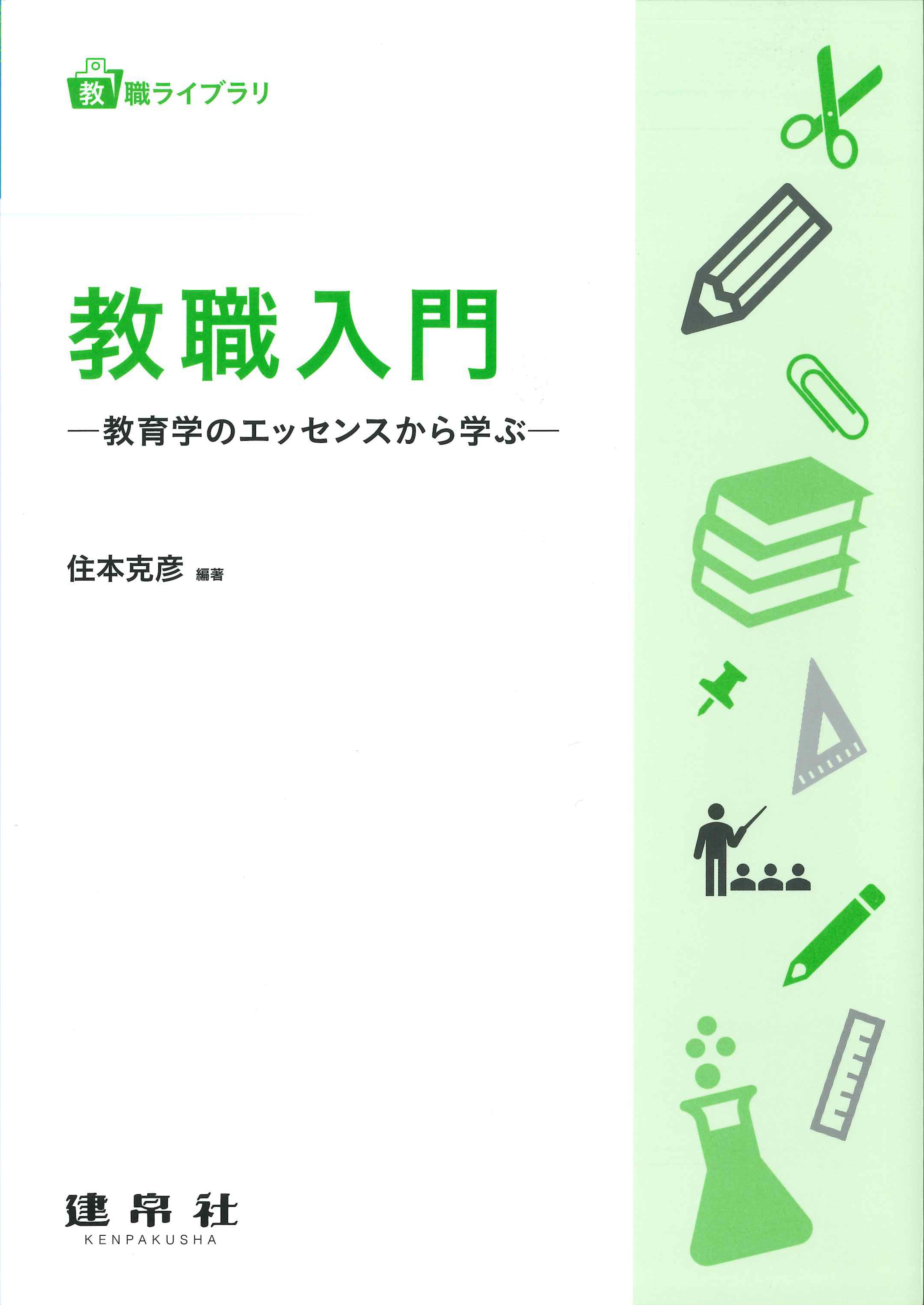
教職入門
教職課程コアカリキュラム「教職の意義及び教員の役割・職務内容」に準拠。教育実習,教員採用試験の章もあり,教職に関する最新の知識を盛り込んだテキスト。
-
-
-
pickup
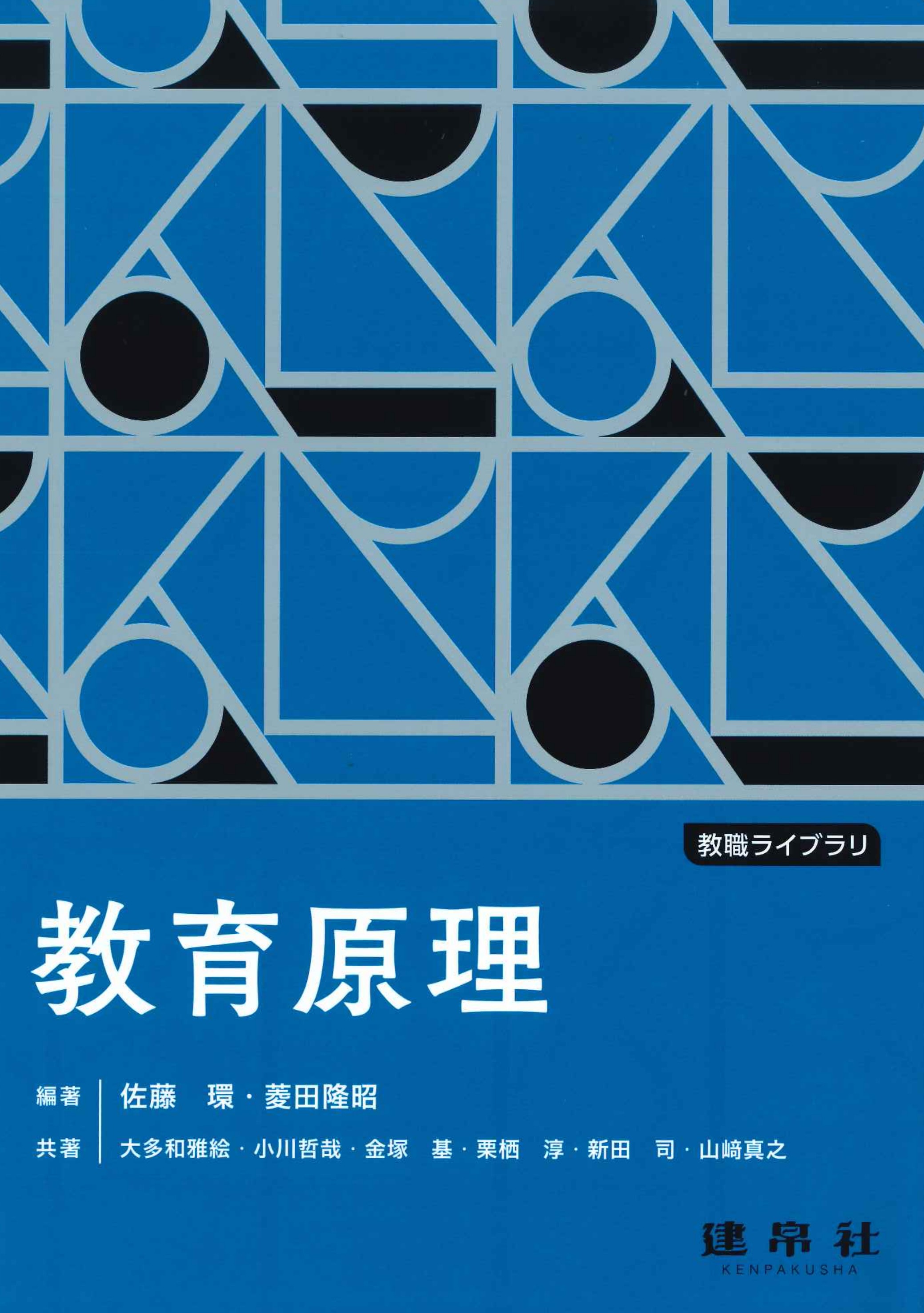
教育原理
教職課程の「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」に対応。教職課程コアカリキュラムを十分に網羅しつつ,教育の本質や今日的課題につながるよう,バランスの取れた構成を心掛けた。
-
-
-
pickup

生徒指導・進路指導論
教員養成課程の「生徒指導・進路指導論」のテキスト。VUCAな時代にあってこれからの教員に求められる指導力の内容を,様々な角度(組織的連携,校則・懲戒・体罰,いじめ,不登校等)から丁寧に解説した。
-
-
-
pickup
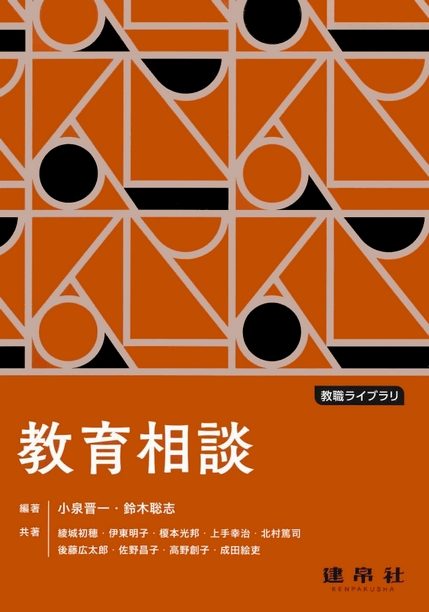
教育相談
教職課程の「教育相談の理論及び方法」に対応。教職課程コアカリキュラムのポイントを押さえつつ,今日的な課題や近年注目されているカウンセリングの要素などについて,実践的な演習を交えて学ぶ。
-
-
-
pickup
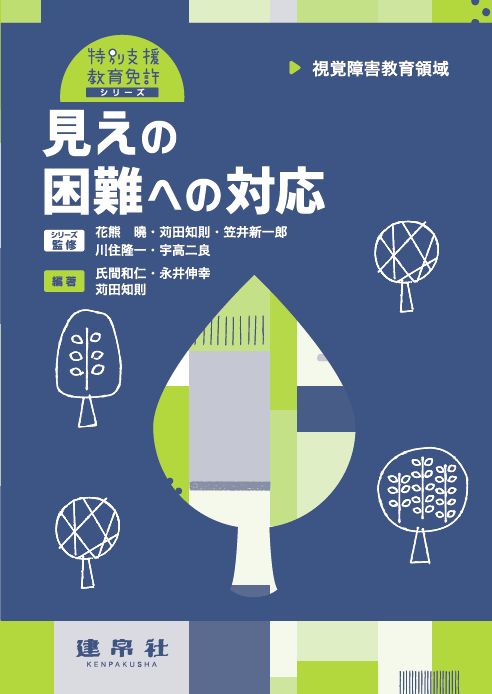
見えの困難への対応
教育における見る機能の意味を理解する。ものを見る仕組み,眼疾患及び心理学的知識を学び,見ることの困難さを改善・克服する支援を習得する。就学前・卒後支援と家庭及び医療機関との連携についても解説。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。