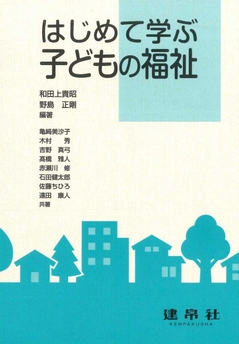各章に「アウトライン」の頁を設け,初学者が要点を把握して概要を俯瞰しながら学習できる,子ども家庭福祉の入門書。今日的な課題・動向をふまえ,前身である『子どもの福祉』からリニューアルを図った。
内容紹介
まえがき
は し が き
わが国における少子化は,政府の想定を遥かに超える勢いで進行している。1994(平成6)年策定のエンゼルプラン以降,わが国では矢継ぎ早に少子化対策を実施しており,2023(令和5)年には「こども未来戦略」を閣議決定し,それに基づく「こども・子育て支援加速化プラン」を打ち出した。また,2022(令和4)年にこども基本法が成立し,翌年には,子どもの育ちの保障や子育て支援に関する施策の司令塔として「こども家庭庁」が発足した。こうした対策により,一昔前に比べると子育てしやすい状況が構築されてはきている。
一方で新たな課題もある。労働力不足の解消を目指した外国人材(外国籍の労働者)の受け入れ急増により,外国にルーツのある子どもたちの就学や就業においてさまざまな問題が生じている。また,ヤングケアラーの問題は,家族の構成人数の減少により,家族機能の維持を子どもが担わせられることから生じている。孤食と呼ばれる子どもが一人で食事をせざるを得ない状況も同様に核家族化やひとり親家庭の増加とそれに対する対策の不十分さから生じる。
このような状況下において,子どもとその家庭の福祉を支える専門職は,十分な知識を身につけ,状況の変化に対応していくことの重要性を理解しなければならない。そのためのテキストとして,本書は次のように構成した。
第Ⅰ部は「子ども家庭福祉の今を学ぶ」とし,子ども家庭福祉の理念および対象ごとの課題や政策,運用状況について解説しており,子ども家庭福祉の基本的な状況を理解することを目的としている。
第Ⅱ部は「子ども家庭福祉の歴史としくみを学ぶ」とし,歴史,法体系,実施機関・施設について学ぶとともに,海外の状況について学ぶことで日本の特徴についてつかめるような内容となっている。
第Ⅲ部は「子ども家庭福祉の実践を学ぶ」とし,保育士を目指す学生たちが身につけるべき専門性について説明している。子ども家庭福祉において専門職が果たすべき役割は多岐に渡る。また連携すべき他の専門職の専門性や職務内容について学ぶことも必要となる。本書を読むことで専門的な技術がすぐに身につくものではないが,現場における視点として,保育士を含む専門職がどのような点に配慮して取り組んでいるのかを理解しておく必要がある。
また,各章に「演習コーナー」を設け,講義を受けるだけでなく,受講生がその章での学びについて,主体的に理解を深めることができるようにした。
本書の前身である『子どもの福祉─子ども家庭福祉のしくみと実践─』は,2000(平成12)年の初版発行以来,時代・状況に合わせて,幾度もの改訂を重ねてきた。そして先述の内容へと改めるにあたり,新たに執筆陣を迎え,『はじめて学ぶ子どもの福祉』と書名も新たにしてこのたび刊行した次第である。
子ども家庭福祉の役割は子どもや子育て家庭,社会の状況に応じて変化してきたが,新たに生じる課題に対応すべく,これからも変化していくことが予想される。そうした変化の中にあっても,子ども家庭福祉について保育士養成課程における我々がすべきことは,適切な価値意識と専門性をもつ職員を養成することである。本書がそれに資することができれば幸甚である。
2025年3月
編 者 和田上貴昭
野島 正剛
目 次
第Ⅰ部 子ども家庭福祉の今を学ぶ
第1章 子どもの福祉と理念
1 子どもと家庭の福祉
2 子どもの人権
3 子ども・家庭と社会の変化
第2章 子どもと子育て支援
1 子どもと家庭を取り巻く状況
2 子育て支援施策の経緯
3 子ども・子育て支援新制度以降の状況と課題
第3章 子どもと保育
1 親の就業状況と保育ニーズ
2 多様化する保育ニーズと保育サービス
3 さまざまな保育サービス
第4章 子どもと虐待・社会的養護
1 子どもの養護問題
2 子ども虐待
3 DVとその防止
第5章 子どもと障害
1 保育者が障害についてなぜ学ぶ必要があるのか
2 障害について
3 障害のある子どもの状況
4 障害のある子どもへの施策と福祉サービス
5 障害のある子どもと家族への支援
第6章 子どもと行動上の「問題」
1 子どもの行動
2 心理的な問題への対応
3 少年非行への対応
4 不登校,ひきこもり,ニートへの対応
第7章 子どもと貧困
1 家庭の経済状態と子ども
2 貧困・低所得家庭の現状と子どもへの影響
3 子どもの貧困に対する取り組み
第Ⅱ部 子ども家庭福祉の歴史と仕組みを学ぶ
第8章 子どもの福祉の歴史
1 欧米の子ども家庭福祉
2 日本の子ども家庭福祉の歴史
3 子どもの権利に関する歴史~国境を越えて~
第9章 子ども家庭福祉の制度と法体系
1 子ども家庭福祉に関する法体系
2 子ども家庭福祉に関する法律
第10章 子ども家庭福祉の実施体系と実施機関,施設
1 子ども家庭福祉の実施体系
2 子ども家庭福祉に関する審議機関
3 子ども家庭福祉の実施機関
4 子ども家庭福祉の施設
第11章 子どもと諸外国の子ども家庭福祉
1 国による子ども家庭福祉施策の違いと背景
2 諸外国の状況
第Ⅲ部 子ども家庭福祉の実践を学ぶ
第12章 子どもの福祉を支える専門職
1 専門職と資格
2 児童相談所で働く専門職
3 児童福祉施設等で働く専門職
4 その他の専門職
第13章 子どもの福祉を支える専門性
1 チャイルドケア
2 ソーシャルワーク
3 他機関・多職種との連携・協働
第14章 子どもの福祉と連携
1 連携の重要性
2 地域における連携・協働
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup
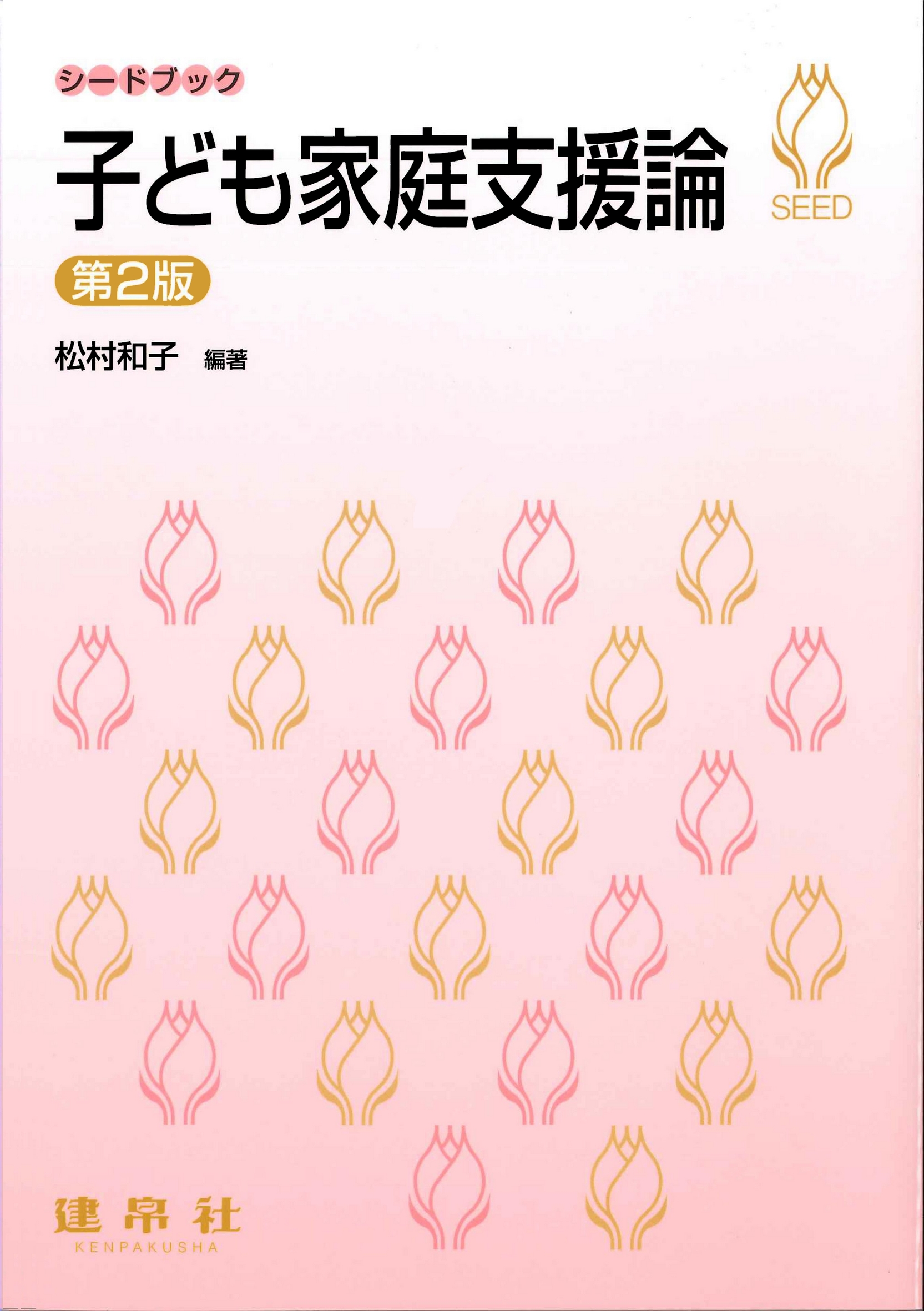
子ども家庭支援論 第2版
保育士養成課程教科書。統計および法令の記述を更新した「第2版」。こども家庭庁ほか,最新の情報に基づき改訂。より充実した内容に。
-
-
-
pickup
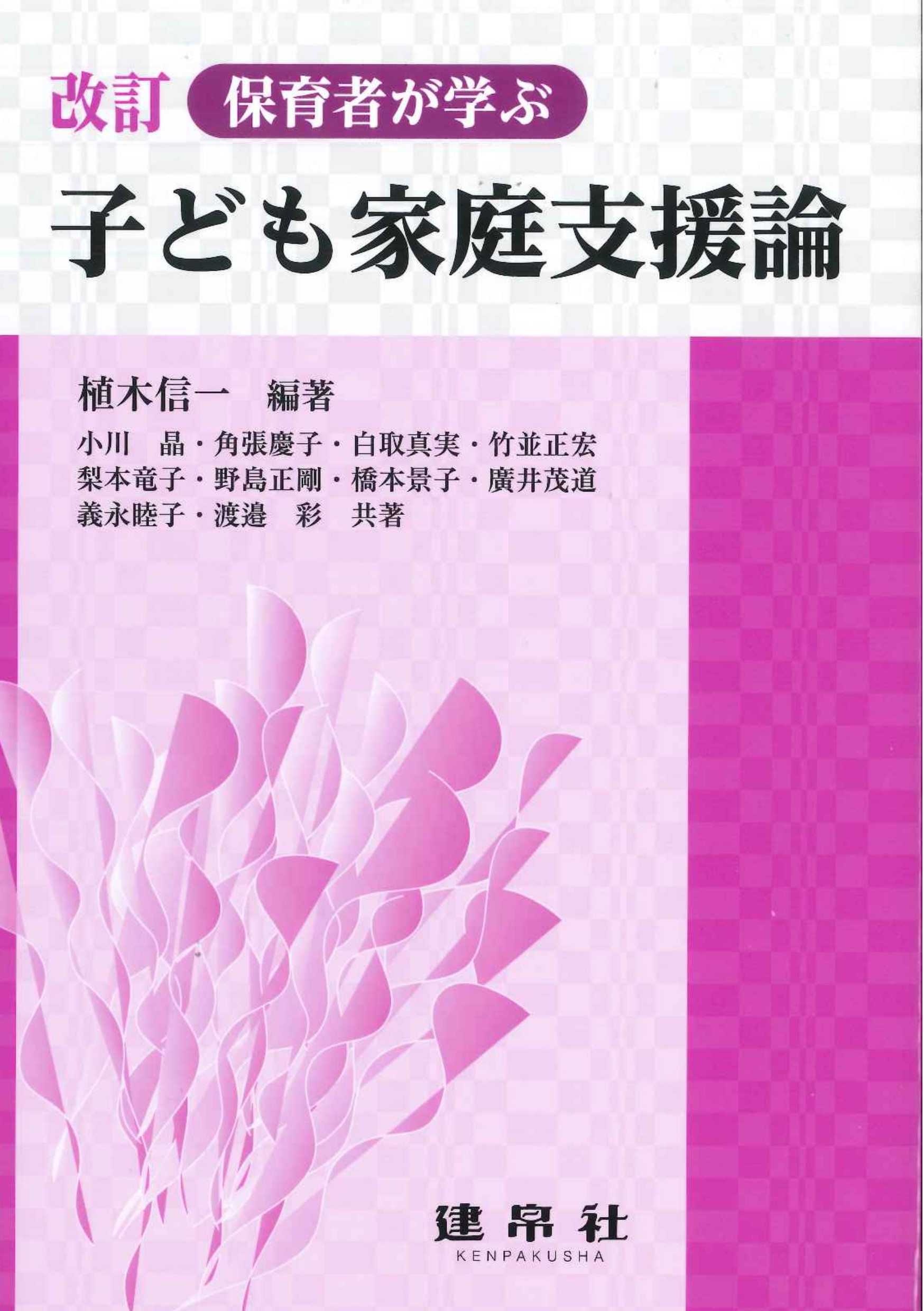
改訂 子ども家庭支援論
保育士養成課程における「子ども家庭支援論」に対応するテキスト。子どもとその家庭への支援についての知識を学ぶだけでなく,巻末の事例編を用い,演習的な学習も可能。法制度の改正に伴う改訂版。
-
-
-
pickup
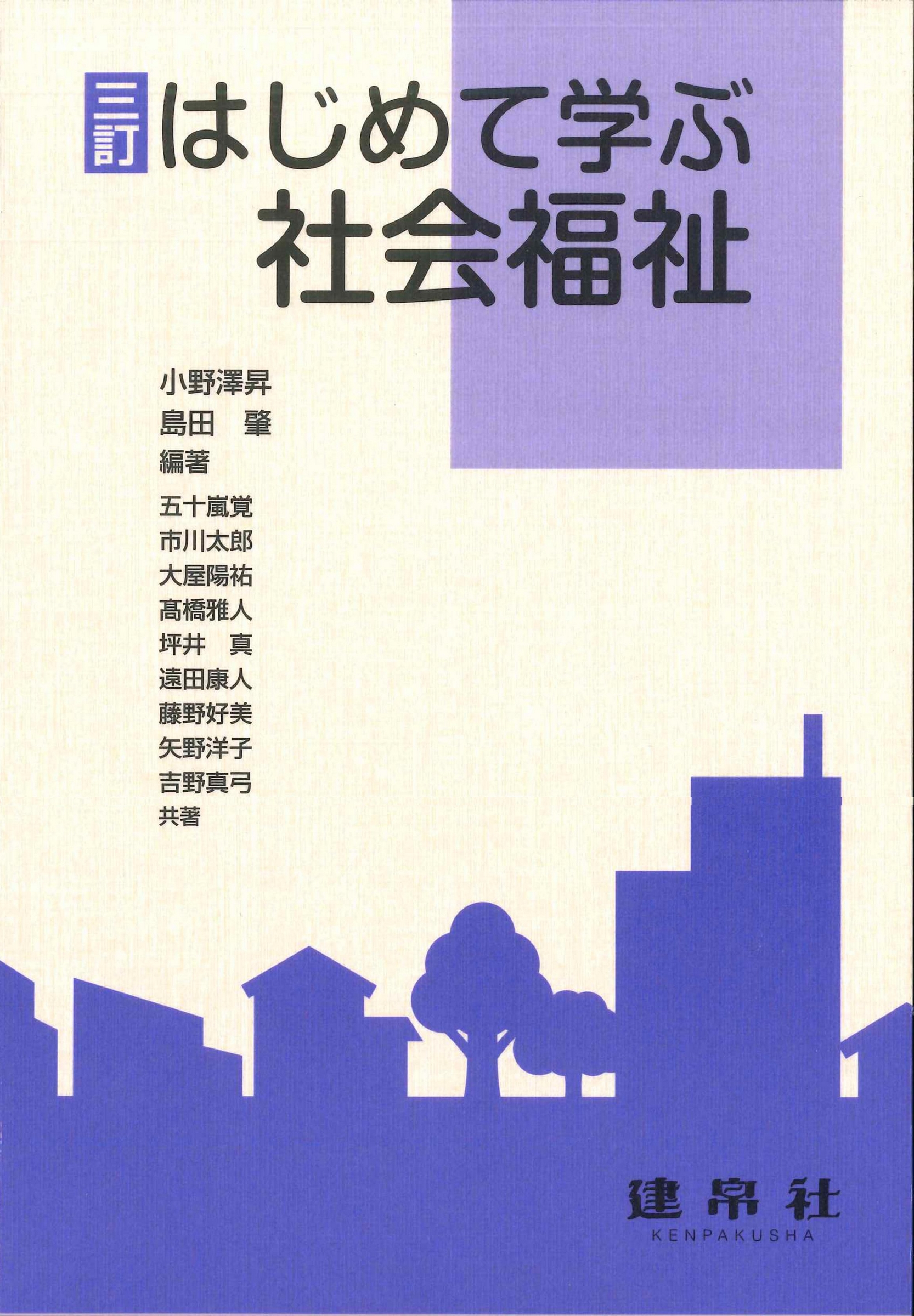
三訂 はじめて学ぶ社会福祉
各章に「アウトライン」の頁を設け,初学者が要点を把握して概要を俯瞰しながら学習できる社会福祉の入門書。社会福祉における各分野の実態や今日的な課題・動向,最新の統計や法改正等を踏まえた三訂版。
-
-
-
pickup
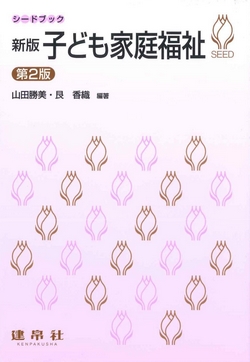
新版 子ども家庭福祉 第2版
保育士養成課程,社会福祉士養成課程ほかの「子ども家庭福祉」(児童福祉論)に対応した教科書。子どもの人権を基盤に据えて,子どもの問題の背後にある社会の問題を意識して論ずる。
-
-
-
pickup
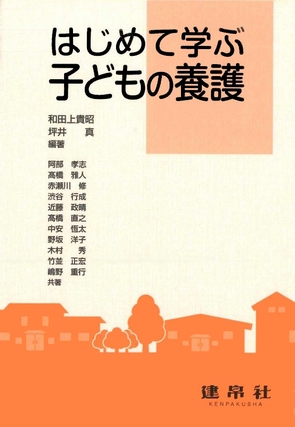
はじめて学ぶ子どもの養護
各章に「アウトライン」の頁を設け,初学者が要点を把握して概要を俯瞰しながら学習できる,「社会的養護Ⅰ・Ⅱ」のテキスト。最新の動向をふまえ,前身である『子どもの養護』からリニューアルを図った。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。