心とからだの健康にとって食事がいかに重要であるか,喫食者に必要な栄養素をおいしい食べ物に整えていかに食卓に提供できるか,調理の科学と健康の科学の接点から「食事」を考える。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」に準拠し,内容を改めた四訂版。
心とからだの健康にとって食事がいかに重要であるか,喫食者に必要な栄養素をおいしい食べ物に整えていかに食卓に提供できるか,調理の科学と健康の科学の接点から「食事」を考える。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」に準拠し,内容を改めた四訂版。
健康志向の高まる中,肥満や高血圧,糖尿病などの生活習慣病を栄養・食生活の面から予防し,国民の健康維持・増進を図ろうとする運動が「健康日本21」を契機に展開されている。本書は,このような時代の社会的要請に調理学も応えていかなければならないという背景を踏まえ,健康づくりの一端を担うべく,ここに『健康・調理の科学―おいしさから健康へ―』と題して出版することにした。
今回の栄養士法の一部改正に伴う管理栄養士教育養成カリキュラムでは,調理学は「専門基礎分野」の「食べ物と健康」の教育内容に該当する。この領域では,食品が加工・調理を経て人に摂取されるまでの過程について学び,人体に対する栄養面,安全面への影響や評価について理解することを目標に掲げている。「食べ物と健康」の教育内容を含む調理学の書籍は多数出版されているが,本書は新たな試みとして「調理科学」へ「健康科学」の視点からアプローチした。
本書の特徴は第3 章「おいしさと健康」にあると考える。ここでは,人が口を通して食べることの意味を問い直し,栄養摂取にとっておいしく食べることの重要性を味覚が果たす栄養・生理的役割の面から理解し,さらに,油脂と砂糖が過剰摂取を招きやすいのはなぜかを食材としての調理加工特性の面から考える内容とした。また,咀嚼・嚥下機能の低下した高齢者への食事対応については,安全性の視点で食物テクスチャーの重要性を理解できるように努めた。また,「食べ物と健康」の領域に位置づけられた食事設計は,第2章「食事設計と健康」として,嗜好を満たしつつ栄養素の適切な摂取可能な食事を実現していくための食事計画の基礎知識を学ぶ内容とした。他の章の構成としては,第1 章「人間と食べ物のかかわり」で環境問題や食文化を取り上げ,第4 章「調理操作の体系化」では,大量調理への応用展開も視野に入れながら,エネルギー源,調理機器,調理操作について学ぶこととした。第5 章「おいしさの形成と健康への影響」は,食品の特性と調理による変化を理解し,おいしさを作り出すための調理法を理解する内容とした。
今日まで調理学は食べ物の嗜好性に焦点をあて,調理過程における食品の成分変化や組織・物性などの変化を通して,おいしさの創造に役だつ理論の構築に主力を置いてきた。近年,あらゆる領域で人間主体の科学が著しく進歩する中,食の分野でもおいしさの認知という人間の側に立った嗜好性の解明が進み,おいしさが人の心身の健康に極めて重要であることが実証されつつある。これからの調理学においては,食べ物のおいしさが,なぜ心と身体の健康にとって大切であるかという人間の側からの理解と,その視点に立った取り組みが一層求められるのではないだろうか。「新しい食生活指針」のメッセージ―「心とからだにおいしい食事」―を乳幼児から高齢者まで,健常者から病弱者まで広く対象者の食卓に実現し,健康増進や疾病予防に貢献できるよう新たな調理学の基軸を打ち立てていくべき時代に直面していると痛感する。本書をご利用いただいた方々から,率直なご意見ご批判を賜れば幸いである。
最後に編者の意図をご理解いただき,ご協力いただいた建帛社の筑紫恒男社長をはじめ関係各位に厚くお礼を申し上げる。
2004 年7 月
和 田 淑 子
大 越 ひ ろ
本書の初版は,2004(平成16)年に「管理栄養士講座」の一巻として出版されたもので,その後「日本人の食事摂取基準」,「日本食品標準成分表」など食にかかわる指針・法令などが相次いで改訂された。本書もその都度,該当する箇所を書き改めて今日に至っている。おかげさまで,多くの管理栄養士養成課程で本書をご利用いただいている。
管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)が2019(平成31)年3 月に改定され,調理学分野のガイドライン修正点として,「日本標準食品成分表の理解」が大項目「食品の分類と食品の成分」から「食事設計と栄養・調理」に移動することになった。それに伴い,第4 章の「食事設計と健康」に「食品成分表の理解と活用」の項目を立て,献立作成に活用できるように組み入れた。
一方,2019(令和元)年12 月に発表された「日本人の食事摂取基準(2020年版)」は,これまでの生活習慣病の重症化予防に加え,高齢者の低栄養・フレイル防止を視野に入れて策定されたもので,本書においてもこの内容を踏まえ,理解できるように考えた。
本書は,初版まえがきにも述べたように,「おいしさと健康」に重点を置いているので,独立させて,第2 章とした。この章は,初版から口を通して食べる意味を理解するための項目として,味覚や嗅覚を感じるからだの仕組みを,栄養・生理学的役割から理解する内容とした。さらに今回の改訂では,「基礎栄養学」のガイドラインの中項目の「消化器系の構造と機能」に,消化は口腔から始まるという理由から,口腔の機能が追加され,口腔期の重要性が認められた。本書では,初版から咀嚼・嚥下機能と食事について,テクスチャーと関連させて理解を深めるようにしてきたが,超高齢社会に向かっている現代において,高齢者の食介護の視点からテクスチャー面の段階的な食事基準にも言及している点でも,他の調理関連の教科書とは視点を異にしている。
本書は四訂まで版を重ねてきたが,まだまだ不十分な点が多いと思われる。本書をご利用いただいた方からのご批判・ご教示をいただければ幸いである。
2020 年2 月
大 越 ひ ろ
高 橋 智 子
1.食べ物と生活環境
2.食べ物と栄養調理
3.日本人と食べ物の歴史的かかわり
Ⅰ おいしさを感じるからだの仕組みと健康への影響
1.口を通して食べる意味
2.味を感じる仕組み
3.味覚の栄養・生理的役割
4.においを感じる仕組みと栄養・生理的役割
5.テクスチャーを感じるからだの仕組み
6.テクスチャーと健康機能―高齢者の食介護の視点から―
Ⅱ 食べ物とおいしさ
1.おいしさに関与する要因
2.おいしさを構成している食べ物の成分
3.おいしさの評価方法
4.ハイドロコロイドが食べ物を食べやすくする
5.油脂の嗜好機能と健康
6.砂糖の嗜好機能と健康
7.食塩の嗜好機能と健康
Ⅲ 調味と味覚
1.調味操作
2.調味と味覚能力
1.調理操作の基礎
2.調理用エネルギー源
3.調理用具と調理機器
4.調理作業のシステム化
5.非加熱調理操作
6.加熱調理操作
7.湿式調理操作と調理機器
8.乾式調理操作と調理機器
9.電子レンジと電磁調理器
10.新調理システム
1.食事の意義と役割
2.食事計画と食事摂取基準
3.食品成分表の理解と活用
4.食品の食事構成
5.献立作成
6.ライフステージと食生活
7.食生活と生活習慣病
8.料理様式と食事構成
Ⅰ 炭水化物を多く含む食品
1.炭水化物の種類と調理プロセスでの変化
2.米と炊飯の科学
3.小麦粉と小麦粉製品の科学
4.いも類・豆類の科学
Ⅱ たんぱく質を多く含む食品
1.たんぱく質の種類と調理プロセスでの変化
2.獣鳥肉類の科学
3.魚介類の科学
4.卵の科学
5.乳・乳製品の科学
6.だいず製品の科学
Ⅲ ビタミン・無機質を多く含む食品
1.ビタミンおよび無機質と調理プロセスでの変化
2.野菜類・果実類の科学
3.きのこ類・藻類の科学
4.種実類の科学
Ⅳ 嗜好品
1.嗜好飲料
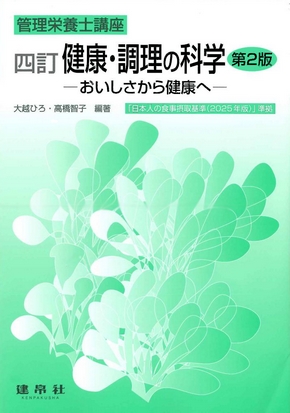
心とからだの健康にとって食事がいかに重要であるか,調理の科学と健康の科学の視点から考える。「日本人の食事摂取基準(2025年版)」に準拠し,内容を改めた四訂第2版。
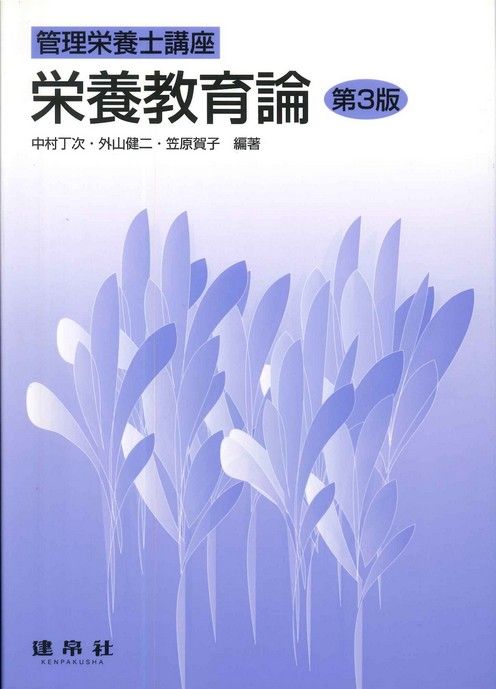
日本人の食事摂取基準(2020年版)等に準拠して改訂。PDCAのマネジメントサイクルに則って成果を出す栄養教育の実施を目指す。
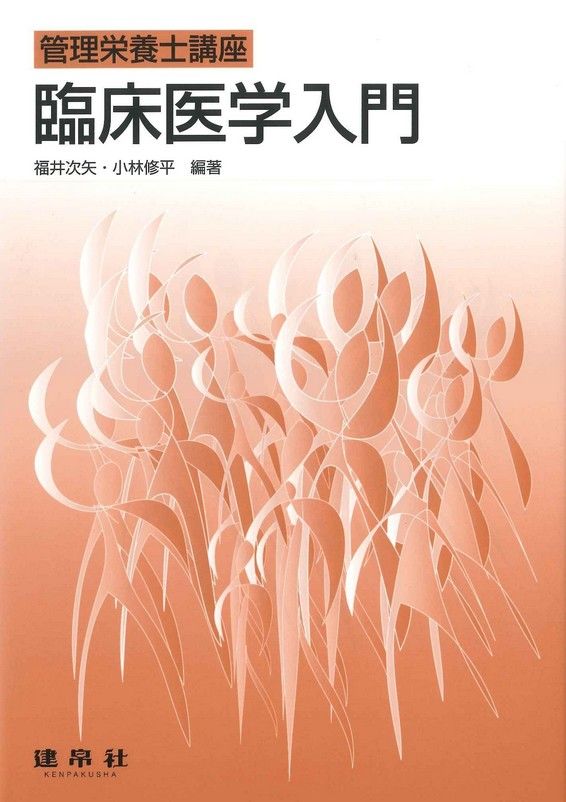
管理栄養士が臨床栄養の現場で活躍する傾向が強まる中で,必要な医学的知識を網羅する一冊。現役医師を中心に最新知見を踏まえ詳述する。
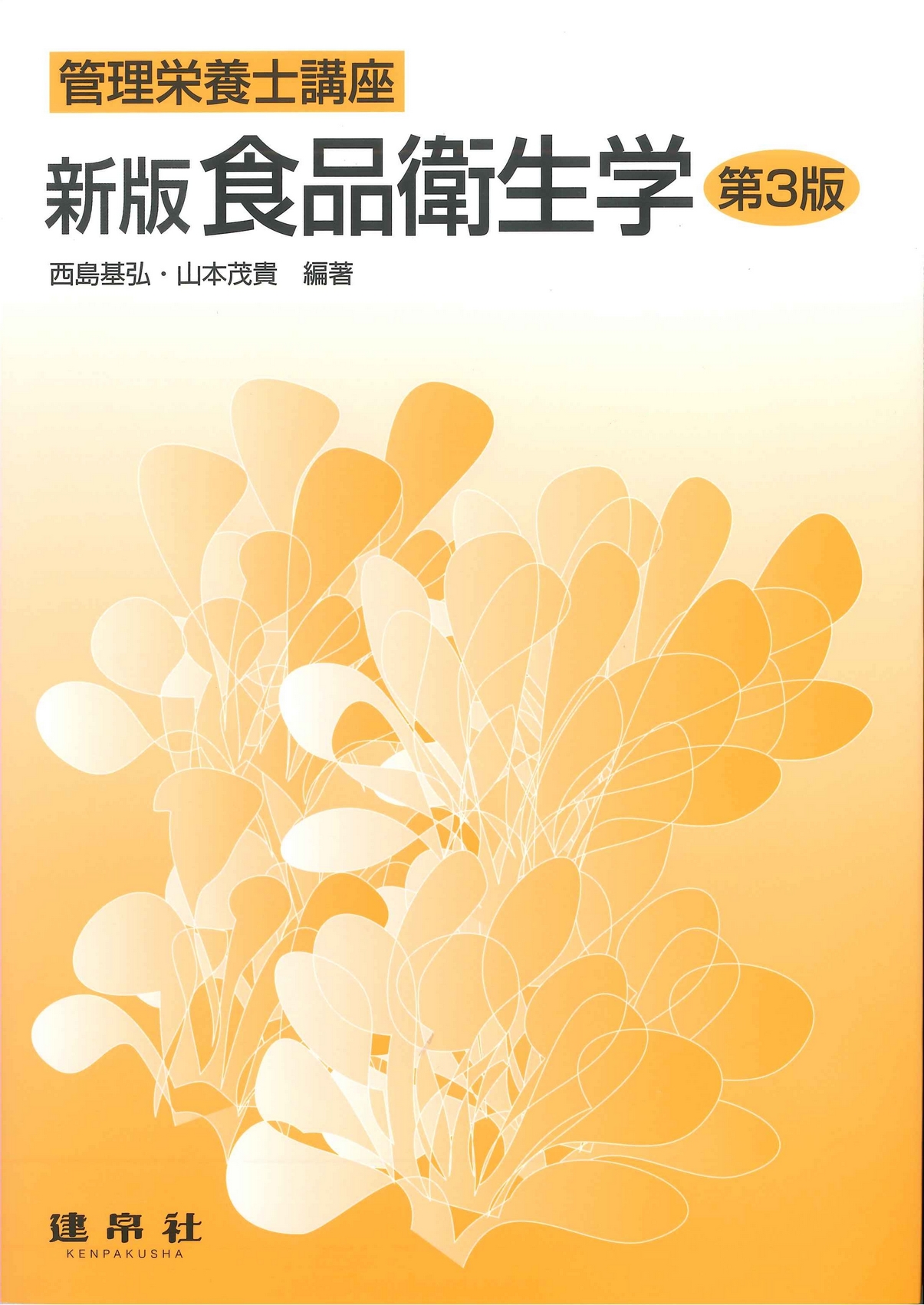
管理栄養士養成課程のための,高い専門性を意識したハイレベルなテキスト。統計情報や規格の記述を改めたほか,食品衛生法の改正や容器包装,HACCPについての最新動向などを加筆し改訂。
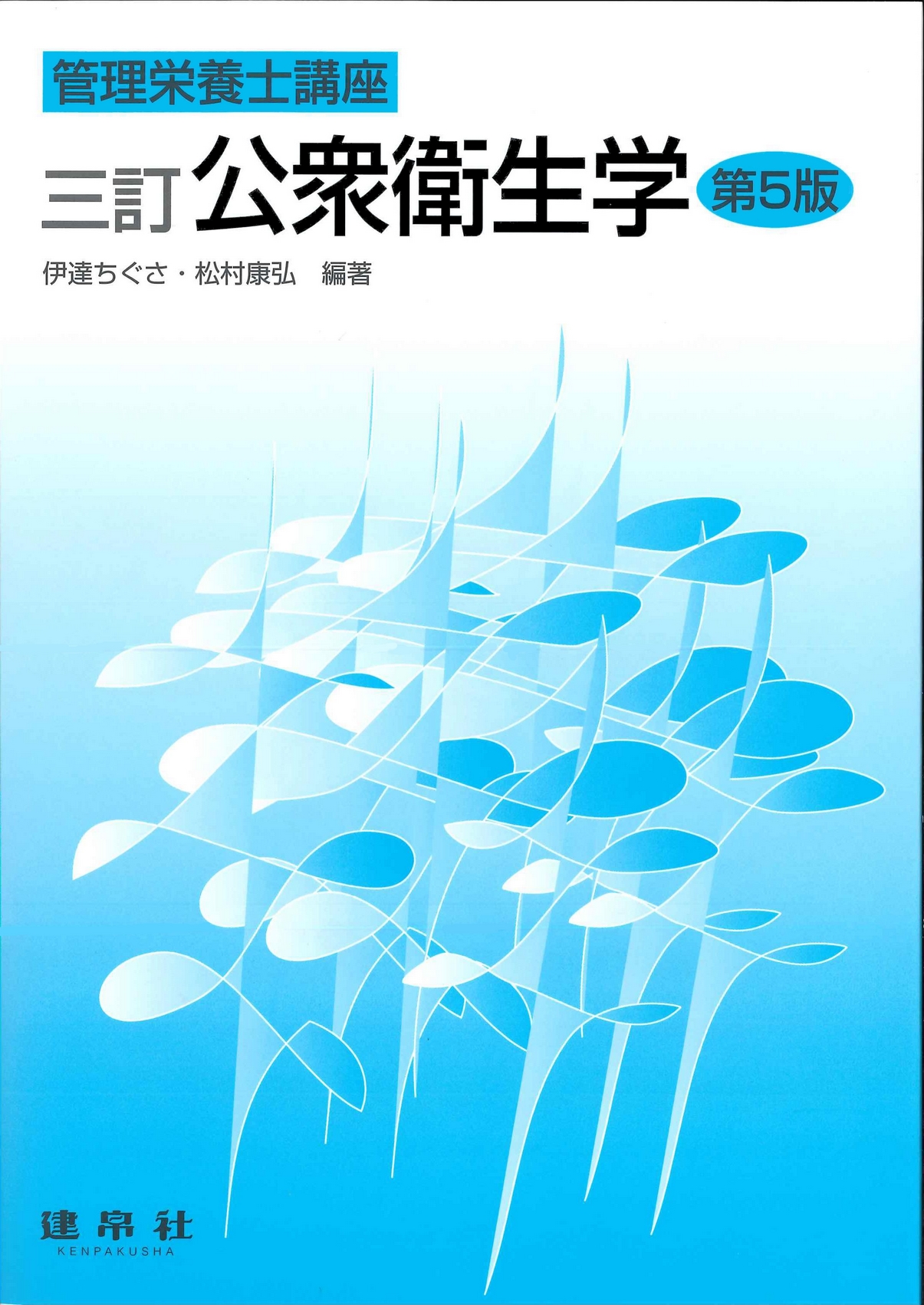
より専門性の高い公衆衛生テキスト。疫学情報や統計・法令を最新知見に更新した第5版。管理栄養士国家試験ガイドラインの改定にも対応。
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。