大量調理に向いた献立作成の方法を理論立てて解説。献立作成の土台となる知識の習得から実習へのつながりを見据え,基礎編と実践編の2部構成とした。 基礎編では給食献立の基本的な考え方,大量調理の基本から,献立の立案,評価までを扱い,実践編では,病院,高齢者介護福祉施設,児童福祉施設,学校,事業所の各施設について栄養管理における留意点をまとめ,具体的な献立例を提示した。
食事摂取基準2020年版,食品成分表2020年版(八訂)のほか,最新の情報に対応。
大量調理に向いた献立作成の方法を理論立てて解説。献立作成の土台となる知識の習得から実習へのつながりを見据え,基礎編と実践編の2部構成とした。 基礎編では給食献立の基本的な考え方,大量調理の基本から,献立の立案,評価までを扱い,実践編では,病院,高齢者介護福祉施設,児童福祉施設,学校,事業所の各施設について栄養管理における留意点をまとめ,具体的な献立例を提示した。
食事摂取基準2020年版,食品成分表2020年版(八訂)のほか,最新の情報に対応。
給食実習を行うにあたり,学生の皆さんに「献立を立ててください」とお願いしてみると,うまく立てられない人が多く見受けられます。料理の食材名を書き出せなかったり,1人分の各材料の必要量を示すことができなかったり,あるいは様々なジャンルからの寄せ集めの献立となり,「カレーライス,みそ汁,ケーキ」,「チャーハン,焼き魚,サラダ,すまし汁」のように,てんでバラバラの多国籍料理となってしまうこともあります。一生懸命考えた献立が,計算上の栄養バランス的には大変良いにもかかわらず,実際の現場では利用できないような場合もあり,そんな献立作成を苦手とする学生の相談を実習の中で多く受けてきました。
その理由を考えたとき,調理の経験や知識の少なさから,料理のレパートリーが少ないのでは?ということがまず思い浮かびました。実際,学生にヒアリングしてみると,「実家暮らしで調理をした経験が少ない」「中食や外食が多い」という人が多く,中には「包丁もまな板ももっていない」というような人もいるほどでした。
また,少人数調理と大量調理の違いに苦心する人も多くいます。ゼリーが固まらない,プリンに“す”が入る,スチームコンベクションオーブンの使い方がわからない,塩やこしょうはどれだけ入れればいいのか,野菜から水が出て味が薄くなってしまうなど,家庭用の道具で作った試作ではおいしくできたのに,いざ大量調理器具で調理してみると,味も,形も,硬さも,出来上がった時の量もまるで予定と違ってしまうことも多く,「こんなはずではなかった」と反省会で涙する姿を見てきました。「大量調理は難しい」と,苦手意識をもってしまう学生も少なくないようです。
こういった状況は,献立作成や大量調理の基本を知らずに立てた,大量調理に向かない献立を用いて,むりやり大量調理を行っていることが引き起こしているに他ならないのです。
そのような学生たちには,調理学・調理学実習をはじめとする,これまで学んだ知識・技術の基本を活かし,理論立てて一歩一歩着実に献立作成の方法を覚えることで,大量調理に向いた献立を立てられるように指導する必要があるのですが,いざそのような教科書を探してみると,しっくりくるものが見つかりませんでした。ですから今回,経験や思いを共有する先生方が力を合わせ,それぞれの得意分野を受け持って,この教科書を作成するに至ったのです。
著者となってくださった先生方とは事前に会議を行い,「何が問題なのか」「どのような時に失敗してしまうのか」「知っていることは何か,また知らないことは何か」「最低限必要な献立作成のための基礎は何か」「必ず教えておきたいことは何か」など,とにかく様々な過去の経験と意見を出し合って,まるでパズルを解くように,広い裾野から高くそびえたつピラミッドを組み立てるように,この本は作成されました。
本書は,献立作成の土台となる知識の習得から実習へのつながりを見据え,全体の構成を基礎編と実践編の2部立てとしました。
基礎編の第1章は「献立とは」として,給食献立の基本的な考え方と,必須となる大量調理の基本について説明させていただきました。第2章では「献立の立案」についての解説が続きます。献立作成に必要な要素をどのような順序で組み立てる必要があるのかを理解していただきたかったからです。そして第3章の「献立の評価」へと続きます。献立は様々な要素が組み合わされて出来上がっているため,評価するにも様々な手法を用いる必要があります。献立の良し悪しについて評価を行い,より良いものにするための「目標達成における評価」を行うことは重要で,PDCA サイクルにおける「C:チェック」をしっかりと行うことによって,次回以降の献立の改善,そして最終的には大量調理の安定供給へとつなげることができるからです。
実践編では「病院」,「高齢者介護福祉施設」,「児童福祉施設」,「学校」,「事業所」の各施設における食を取り巻く状況や,栄養管理における留意点を述べた後に,具体的な献立例を提示しました。基礎をしっかりと,一つ一つ順番に積み重ねるように学習すれば,献立作成は必ずできるようになります。そして献立作成が楽しく,面白いものであることがわかっていただけると思います。また,バランスの良い献立で作った料理は生活に潤いを与え,健康の維持・増進へつながることもわかっていただけると思います。
さらに,献立がしっかりと立てられるならば大量調理もおのずとスムーズに行うことができるようになります。献立がよければ,少ない人数で,短時間に,おいしく,見栄えの良い食事の作成が可能だからです。
「献立作成は難しくはない」,「大量調理は怖くない」,「必ずできる」ことを一緒に体験していただき,皆さんに自信をもって社会で活躍する栄養士・管理栄養士となっていただくことを心から願っております。そのためにこの教科書が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
さあ,一緒に楽しく「献立作成」を行い大量調理に挑戦しましょう。
2016年4月
編 者
2019年12月に「日本人の食事摂取基準(2020年版)」が厚生労働省から,2020年12月には「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」が文部科学省から公表されました。
また,2016年の本書刊行より5年が経ち,管理栄養士・栄養士,給食に関連するその他のガイドライン等にも変更・改定がなされています。
それらの内容を反映させるとともに,より使いやすい教科書となるよう記述の見直しなどを行い,改訂版として刊行いたします。
これまで同様,本書をご活用いただければ幸甚です。
2021年3月
編 者
第1部 基礎編
第1章 献立とは
1 献立の意義と目的
2 献立作成の基本要素
3 大量調理の基本
第2章 献立の立案
1 コンピュータの利用
2 基本計画
3 献立計画立案
4 献立表の作成
第3章 献立の評価
1 栄養評価
2 食材料評価
3 品質評価
4 顧客管理・マーケティング評価
5 その他の分析
第2部 施設別実践編
第4章 病 院
1 食事療養の意義
2 給与栄養目標量の設定
3 展開食と献立例
4 危機管理対策(災害時)の病院の備蓄品
第5章 高齢者介護福祉施設
1 はじめに
2 介護保険制度におけるしくみと施設
3 高齢者介護福祉施設の給食
4 栄養管理計画
5 献立計画作成
6 献立例
第6章 児童福祉施設
1 児童福祉施設給食の目的・意義
2 栄養管理の重要性
3 食育の目標と給食
4 献立作成での要点
5 献立作成の実際
6 献立例
第7章 学 校
1 学校給食の位置づけ
2 給与栄養目標量の設定
3 献立例
第8章 事業所
1 事業所給食における食を取り巻く状況
2 食事の提供および栄養管理に関する留意点
3 給与栄養目標量の設定
4 献立例
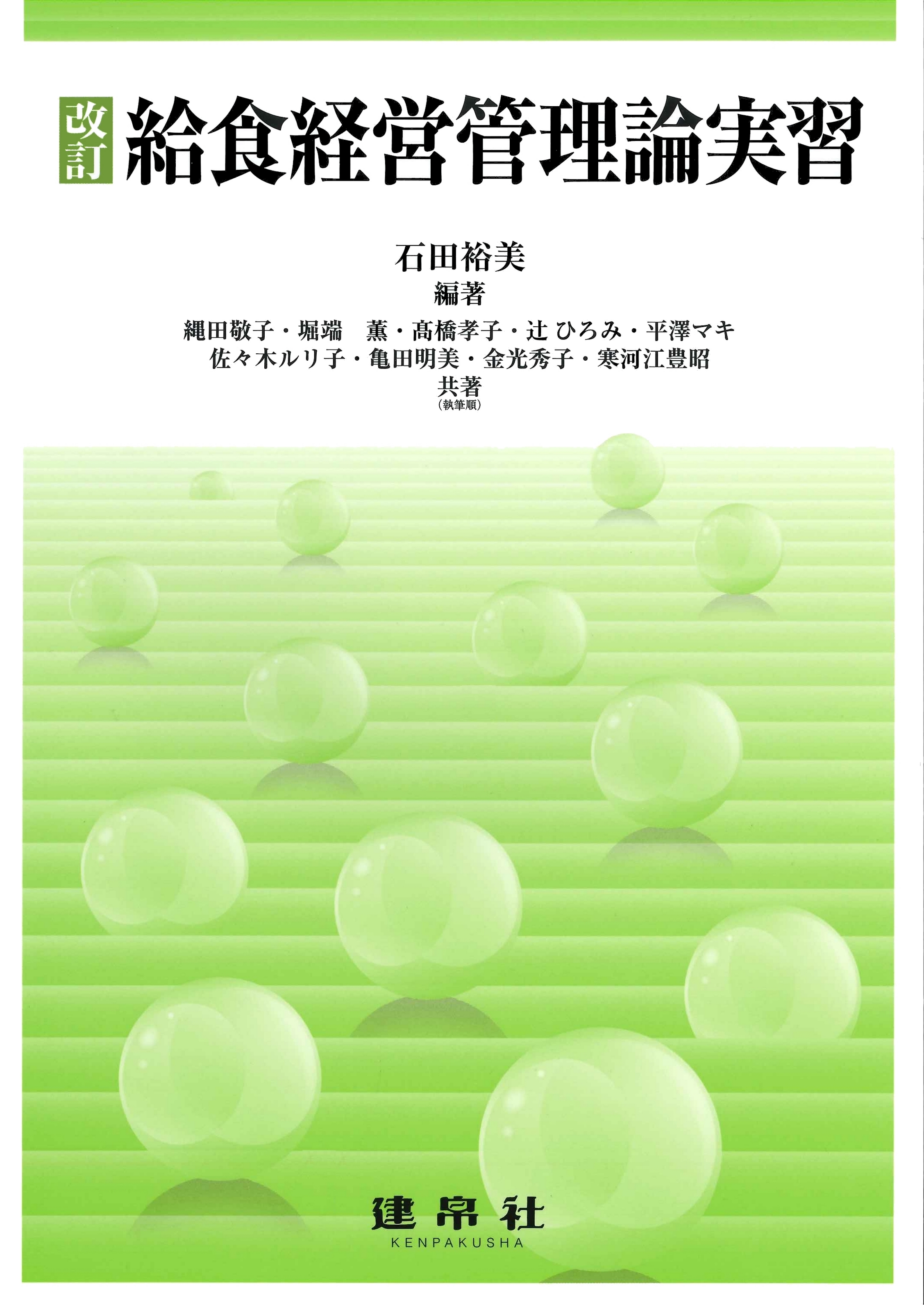
実際の帳票類を通して給食運営管理の全体像を把握し,体系的に学ぶ実習書。食事摂取基準,食品成分表ほか法令等の改正にも対応した改訂版。
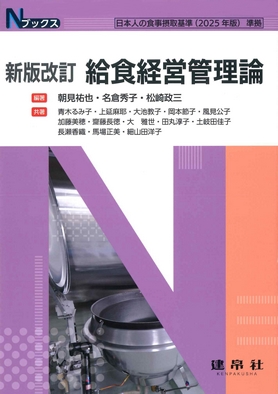
管理栄養士養成課程教科書。実践の場で役立つ学びを重視し、管理栄養士が実際の現場で直面する「マネジメントの手法」をわかりやすく説く。大きく変化する給食を取り巻く環境について、最新の情報を提供。
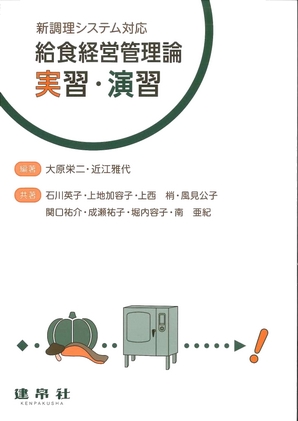
実習の基本的な流れやポイント,実践に即した帳票の書き方(手順)を丁寧に解説。豊富な帳票はダウンロード可能で,記入の演習に活用できる。給食現場で広く普及する新調理システムにも動画資料付きで対応。
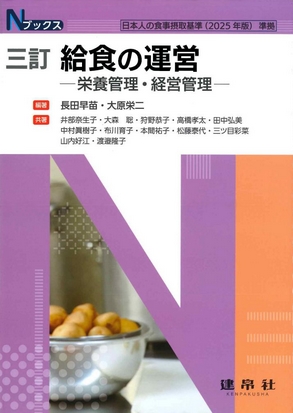
2024年公表の栄養士実力認定試験出題基準(ガイドライン),および日本人の食事摂取基準2025年版に準拠した給食管理の教科書。食物アレルギーについても記載する。
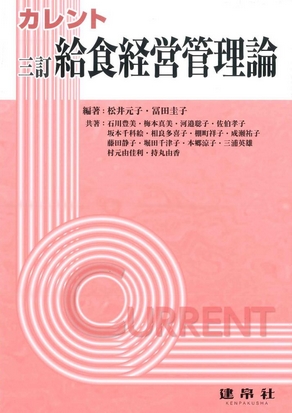
管理栄養士養成向け給食経営管理論の教科書。日本人の食事摂取基準(202年版)等,最新の情報に沿う。
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。