栄養士・管理栄養士養成課程における,校外実習・臨地実習のテキスト。 実際の実習現場での経験豊富な著者により,「ヒトをみることの重要性」を意識できる機会としての実習をめざす。 最新の情報を取り入れ,給食経営管理論(臨地実習),給食の運営(校外実習),臨床栄養学(臨地実習)および公衆栄養(臨地実習)それぞれの実習の基本的な進め方について述べる。
最新の情報に対応した改訂第2版。
栄養士・管理栄養士養成課程における,校外実習・臨地実習のテキスト。 実際の実習現場での経験豊富な著者により,「ヒトをみることの重要性」を意識できる機会としての実習をめざす。 最新の情報を取り入れ,給食経営管理論(臨地実習),給食の運営(校外実習),臨床栄養学(臨地実習)および公衆栄養(臨地実習)それぞれの実習の基本的な進め方について述べる。
最新の情報に対応した改訂第2版。
2002年の改正栄養士法の施行から,すでに15年が過ぎようとしています。この間,改正栄養士法が意図した人間栄養学の内容が徐々に浸透し,管理栄養士・栄養士の職業意識,さらには業務内容が大きく変化してきました。周知のように,管理栄養士・栄養士の職場は,病院や介護施設,給食施設,栄養教諭・家庭科教諭あるいは地域保健の場,食品関連企業での研究開発・営業など多岐にわたりますが,いずれの職場においても,「食」「栄養」「健康」の3つのキーワードは,常に管理栄養士・栄養士の背中についてまわります。管理栄養士・栄養士は,今や献立・調理のみに全力投球して食を提供すれば良いといった対物職業にとどまらず,食がヒトの体内で,どのように栄養となり,ヒトに対していかなる影響を及ぼすのかを考え,人の健康を担う職業,換言すれば,人間栄養学をベースとした対人職業を担わなければなりません。
さて,本書の題名でもあります臨地実習および校外実習は,管理栄養士・栄養士を目指す学生が,人間栄養学を理解する絶好の機会といえます。実習現場には,職場の理念があり,チームがあり,何よりもクライアントであるヒトが存在し, 「ヒトをみることの重要性」,すなわち,人間栄養学を意識させてくれます。同時に,実習現場には幅広いコミュニケーションも存在します。このような実習の機会を十分に享受できるよう,実際の実習現場での経験豊富な筆者らで検討を重ね,本書の企画に至りました。
まず,「第1章 臨地実習および校外実習オリエンテーション」で,実習の目的や意義を明確にし,実習先で物怖じしないように,十分な準備ができるよう配慮しました。「第2章 臨地・校外実習施設」では,それぞれの実習先での各段階における実習の方向性,すなわち「どのようなことができるのか」,「どのようなことをするのか」を提案しています。これらは,養成校の先生方,実習先で指導いただく先生方が,それぞれの実習場面において本書を活用しやすく,また,実習生には自ら考える機会を与え,実習を「単なる思い出づくりの職業体験」に終わらせないための工夫です。
改正栄養士法の施行からの月日の流れとともに,社会全体として臨地・校外実習への取り組み体制は整いつつあります。一方,栄養を取り巻く現状は,刻一刻と変化しています。栄養学,医学の進歩然り,栄養関連の法令も新しいものが次々と制定されています。学生のみならず養成校の教員,あるいは実習現場で指導に携わってくださる先生も,毎日の勉強を欠かすわけにはいきません。
本書は,こうした現状を鑑み,最新の情報を取り入れ,給食経営管理論(臨地実習),給食の運営(校外実習),臨床栄養学(臨地実習)および公衆栄養学(臨地実習)それぞれの実習の基本的な進め方を記載しています。もちろん,本書の内容が,実習のすべてを網羅できているわけではありませんが,管理栄養士・栄養士を目指す学生,養成校あるいは実習施設の先生方の少しでもお役に立てれば幸甚です。
最後に,本書の刊行に際し,多大なご尽力を賜りました建帛社の皆様に感謝致します。
2016年3月
編者記す
近年,ますます高齢化がすすむ我が国において,栄養ケアの重要性がさらに認識されるようになりました。令和3年度介護報酬改定では,高齢者施設の栄養ケア・マネジメントの未実施は減算され,さらに栄養マネジメント強化加算が新設されました。また,令和2年度,および令和4年度診療報酬改定では,ICU等における早期栄養介入管理加算,周術期栄養管理実施加算,入院栄養管理体制加算(特定機能病院における管理栄養士の病棟配置)などの急性期医療分野での新設など,栄養管理に関する多くの項目が見直されました。さらに,令和6年度の診療報酬・介護報酬同時改定では,「リハビリテーション,栄養管理,口腔管理」を多職種が連携して推進することが評価されることとなりました。その結果,診療報酬における「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」,介護報酬では「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養,口腔の一体的取組等」が新設され,栄養士・管理栄養士の役割は一段と注目されています。また,栄養ケア・マネジメントには欠かせない栄養アセスメント指標の標準化に向けて,世界基準であるGLIM基準を使用する動きが進められています。一方,行政分野も同様に,それぞれの自治体に合った介護予防事業を展開されるようになり,行政栄養士にはPDCAサイクルに基づいて自ら施策を実行する能力が求められています。
こうしたことから,この度臨床栄養学と公衆栄養学分野を中心に,管理栄養士・栄養士における臨地・校外実習内容を見直し,この度,「改訂第2版」としました。是非,新しくなった本書を多くの養成校で活用していただければ幸いです。
2025年4月
加藤昌彦・塚原丘美
第1章 臨地実習および校外実習オリエンテーション
1. 臨地実習および校外実習の目標と意義
2. 臨地実習・校外実習の種類および単位数
3. 「給食の運営」と「給食経営管理論」の教科目標・実習内容の相違
4. 実習施設と実習単位の配分
5. 臨地実習・校外実習の事前教育
6. 臨地実習・校外実習の事後教育
● 帳票
様式1:臨地実習・校外実習票
様式2:実習生 プロフィール票
様式3:実習生出勤簿
様式4:臨地実習・校外実習 体調管理表
様式5:実習の自己評価
様式6:臨地実習・校外実習報告書
第2章 臨地・校外実習施設
Ⅰ. 臨床栄養学(臨地実習)
病院等
1. 実習の目的・目標
2. 実習の内容
3. 1週間および2週間の実習日程例
4. 研修課題(個別学習テーマ)
5. 実習の評価
Ⅱ. 公衆栄養学(臨地実習)
保健所・保健センター
1. 実習の目的・目標
2. 実習の内容
3. 1週間の実習日程例
4. 研修課題(個別学習テーマ)
5. 実習の評価
Ⅲ. 給食の運営,給食経営管理論
Ⅲ-1. 給食の運営(校外実習)
医療施設,福祉施設,学校,事業所等
1. 実習に出るにあたって
2. 実習の目的・目標
3. 実習の内容
4. 1週間の実習日程例
5. 研修課題(個別学習テーマ)
6. 実習の評価
Ⅲ-2. 給食経営管理論(臨地実習)
A. 医療施設
1. 実習の目的・目標
2. 実習の内容
3. 1週間の実習日程例
4. 研修課題(個別学習テーマ)
5. その他
6. 実習の評価
B. 福祉施設
1. 実習の目的・目標
2. 実習の内容
3. 1週間の実習日程例
4. 研修課題(個別学習テーマ)
5. その他
6. 実習の評価
C. 事業所
1. 実習の目的・目標
2. 実習の内容
3. 1週間の実習日程例
4. 研修課題(個別学習テーマ)
5. その他
6. 実習の評価

「臨地・校外実習」は重要な専門職育成プログラムに位置づけられている。より教育効果の高い実習を目指して,準備の段階から実習後の学び方までを,豊富な具体例を示しながら順序立てて解説した。
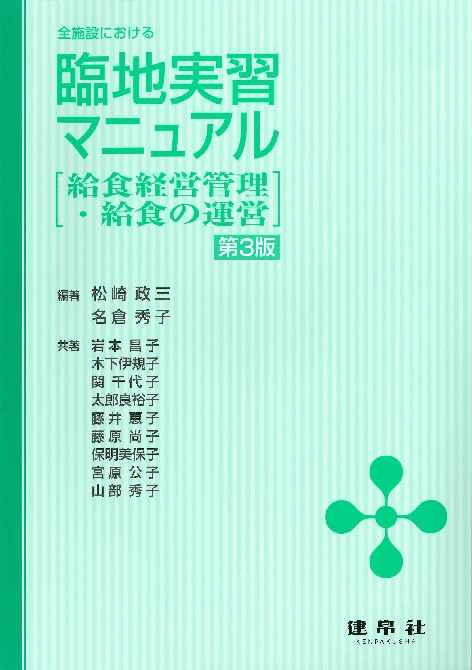
実習施設ごとに具体的な特徴を取り上げ,臨地実習での問題発見・解決の具体的方策,まとめと報告の具体例,注意事項などを説明。
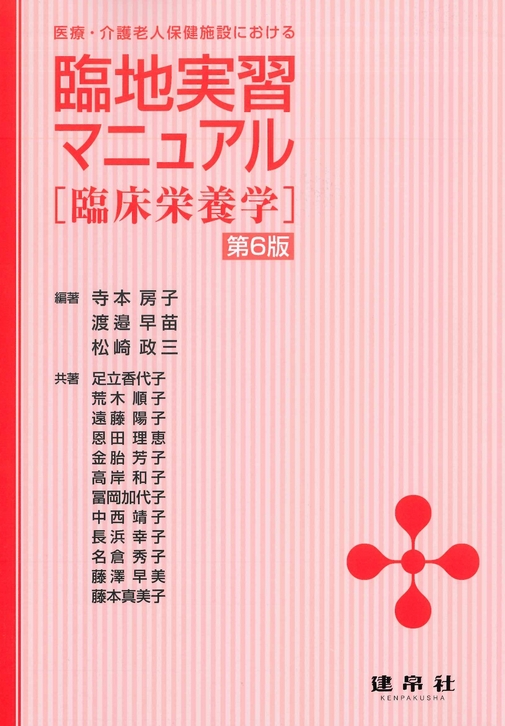
管理栄養士養成課程の臨地実習のためのテキスト。医療施設と介護老人保健施設について,施設の特徴,実習の内容等を簡潔にまとめる。実習に必要な用語,法令等を掲載。
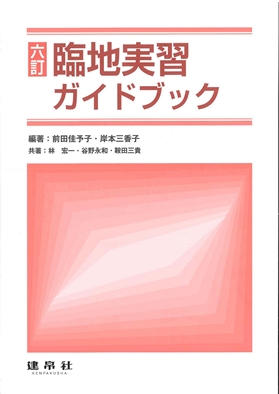
学生が実習内容について明確なイメージをもって積極的に自らが動いて,考え,気づくよう促すために,各施設における具体的な実習スケジュールや課題の取り組みの実例を示し,学習していく。
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。