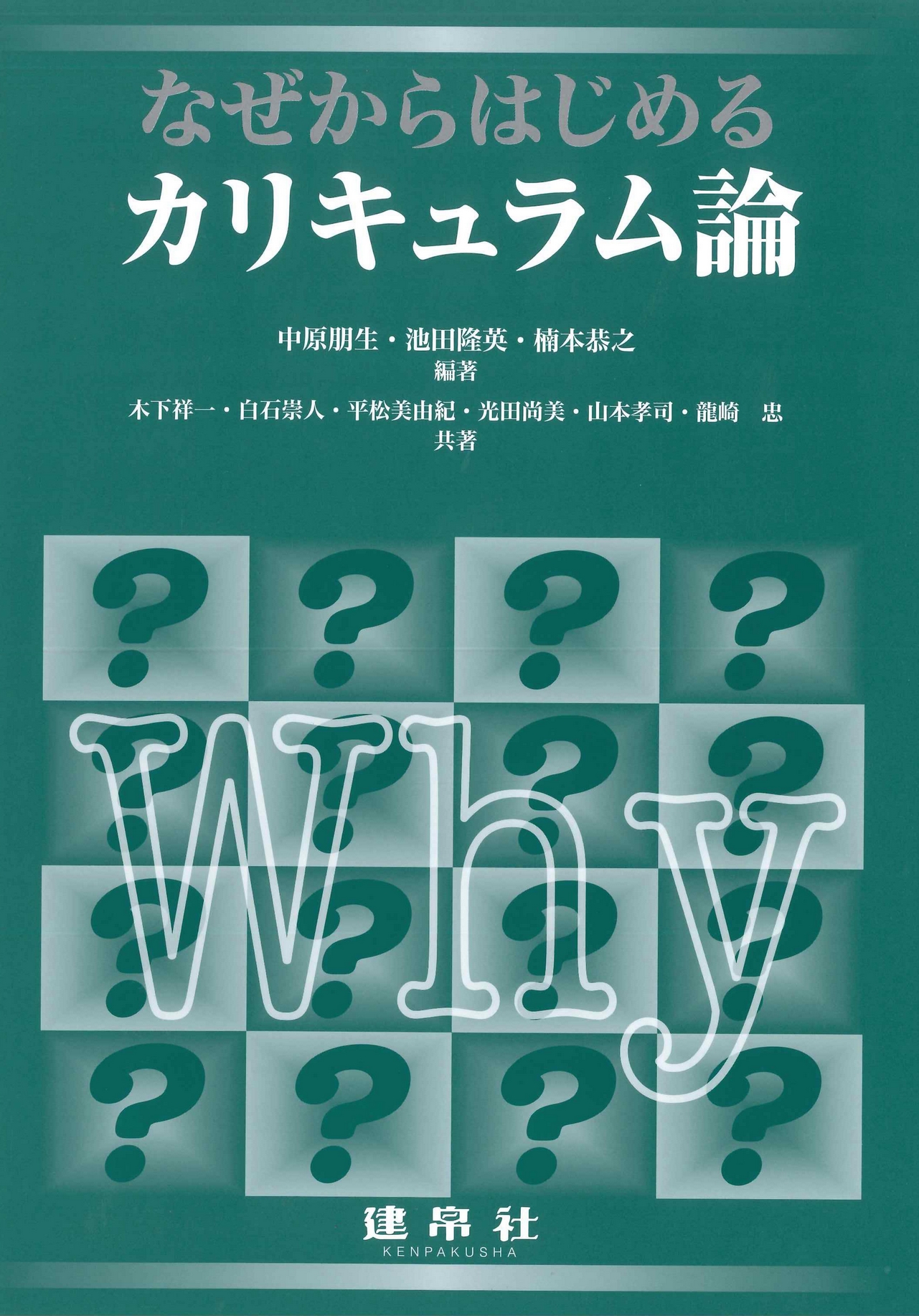「なぜから」シリーズの3冊目になる,就学前保育から就学後教育を見通した「カリキュラム論」のテキスト。各章の最初に「なぜ」「どうして」の問いを設定し,問いに答えていくユニークな構成になっている。
内容紹介
まえがき
は じ め に
本書は「なぜから」シリーズの 3 冊目(既刊『なぜからはじめる保育原理』,『なぜからはじめる教育原理』)で,タイトルに「なぜから~」とあるのは,「問いに答える」「根拠を伝える」というコンセプトである。養成課程で使われるテキストの多くは,「こうあるべき」と価値に基づいて主張する「べき論」であるのに対して,本書は「現にそうある」と事実に基づいて記述する「ある論」を想定している。執筆・編集に携わる私たちが心掛けていることは,「内容を精査すること」「表現を簡潔にすること」であり,「オーソドクシー(定説)」だけでなく「アップデート(最新)」を反映することである。
これまでに刊行した「なぜから」シリーズでの 2 冊と異なる点がある。 1 点目は,各章が「バラバラ」ではなくある程度の「まとまり」を意識した「ユニット」になっていること。 2 点目は,原理や歴史を学ぶ「WHY 型」(第 1 ~ 9 章)に加えて,指導の計画までを見通せる「HOW 型」(第10~15章)となっていること。これらは,近年の「教職科目の共通開設」や「アクティブラーニング」の動向を反映したものとなっている。「ユニット」によって複数の章が関連付けられ,かつ「WHY 型」と「HOW 型」が連動している,ということである。「ユニット」と各章の対応関係は以下の通りで,「まとまり」として整理できる。
1 .教育課程の原理 第 1 章
2 .教育課程の歴史 第 2 章・第 3 章/第 4 章・第 5 章
3 .教育課程の目標と内容・方法 第 6 章・第 7 章・第 8 章
4 .教育課程の管理 第 9 章・第10章
5 .教育課程の実際 第11章・第12章/第13章・第14章/第15章
さらに,「カリキュラム論」のテキストとしては稀有な特色が 2 つある。 1 つ目は,カリキュラムを構成している,学習の指導を行う「教育」の側面と,健康の指導を行う「管理」の側面,という 2つの側面を視野に入れていることである。 2 つ目は,「対象理解に基づいた内容・方法から成る」という原理に沿いながら,対象理解として,「目の前の子どもの姿」だけでなく,人間を長い歴史の流れの中に位置付け,教育を時代や地域の中に位置付けていることである。指導を適切かつ十分に行うには,本書で概説しているような,多くの事項を踏まえる必要がある。
実際に指導を行う場面でも,原理(第 1 章)や展望(第15章)をもちながら,目の前にいる子どもたちの姿の理解(第 6 章)を起点に,教育の内容・方法(第 7 章・第 8 章)や管理の内容・方法(第 9 章・第10章)を考えるものである。しかし,こうした理解・内容・方法は,先達が行ってきた営み(第 2章・第 3 章),それに基づいた制度の成り立ち(第 4 章・第 5 章)を土台に築かれている。また,指導は,就学前保育(第11章・第12章)から就学後教育(第13章・第14章)までを見渡して初めて,子どもの育ちの連続性を担保できる。
こうした学びは,学生の皆さんにとって,一見「役立つもの」には思えないかもしれない。しかし,どんなことも,私たちの「役立てかた」が重要である。本書を執筆・編集をした私たちは,就学前・就学後のどこかで,指導経験がある。「現場」に出ていくと,養成課程で学んだことは,「無駄なものはない」「むしろ足りない程」だと実感する。学びは私たちに開かれている。
2024年 3 月
編者一同
目 次
第1章 社会の中の教育課程 「なぜ学校で教育するのか?」
1.「カリキュラム」という概念
2.「カリキュラム」を支えるもの
3.公教育という制度
4.指導・学習のフレームワーク
5.具体的展開に必要な発想
6.広く深い不断の学びへ
第2章 欧米における教育課程の形成(1) 「なぜ教育課程が生まれたのか?」
1.古代の社会における学び
2.中世前期ヨーロッパにおける学び
3.中世後期ヨーロッパにおける学び
第3章 欧米における教育課程の形成(2) 「なぜ公教育制度が整備されたのか?」
1.市民社会の形成期の教育思想
2.近代における教育の理論と実践
3.近代公教育制度の確立
4.20世紀前半における教育の理論と実践
第4章 日本における教育課程の理念(戦前) 「なぜ社会・国家のために教育するのか?」
1.江戸期における教育課程
2.明治以降から戦前日本の教育課程
3.戦前日本における教育課程の理念
第5章 日本における教育課程の理念(戦後) 「なぜ学習指導要領に基づいて教育課程を編成するのか?」
1.経験主義の学習指導要領
2.系統主義の学習指導要領
3.新しい学力観
4.学校教育における「学力の3要素」
5.就学前教育課程の理念
第6章 教育課程のための子ども理解 「なぜ教師は子ども一人ひとりに目を向けるのか?」
1.カリキュラムを「社会」に近づける
2.発達段階を踏まえて具体的に見る
3.「障害/健常」という理解を超える
4.「明確な基準」のわかりにくさ
5.子ども理解を始める・深める・広げる
第7章 就学前保育の目標と内容・方法 「なぜ遊びを通して学ぶのか?」
1.就学前保育の根拠の概要
2.就学前保育の計画されたカリキュラム
3.指導案作成のコンテンツ
4.指導案作成のための準備
5.要録の記入と就学先の決定
第8章 就学後教育の目標と内容・方法 「なぜ強化を通して学ぶのか?」
1.就学後教育の目的と目標
2.教科教育の成り立ちと拝啓
3.教育方法の変遷
第9章 教育課程の根拠法令 「なぜ運動会を行うのか?」
1.学校教育活動の根拠となる法令
2.保育所における保育活動の根拠となる法令
第10章 教育課程の運営管理 「どうやって運動会を行うのか?」
1.小学校における管理の実際
2.保育所における管理の実際
第11章 遊びによる学びの実際(理解と計画) 「どうやって主体性を育てるのか?」
1.対象理解の観点と発達過程
2.対象理解と保育者の関わりとの相互関連性
3.対象理解に基づく指導計画の立案
第12章 遊びによる学びの実際(実践と評価) 「どうやって個に応じた保育をするのか?」
1.人的環境としての保育者
2.保育における評価
第13章 教科による学びの実際(指導計画と実践) 「どうやって主体的な学びを保証するのか?」
1.計画としてのカリキュラムの構造
2.単元指導計画の作成
3.主体的な学びを保証するための本時指導
第14章 教科による学びの実際(実践と評価) 「どうやって成績をつけるのか?」
1.評価とは何か
2.具体的な指導場面に見る評価
3.多様な評価の方法
第15章 教育課程の課題と可能性 「どうやって社会で生きていくのか?」
1.特別な教育的ニーズのある子どもたちへの教育
2.チーム学校―学校における多様な専門人材による協働―
3.教育機会の確保―学校以外の多様な学びの場での教育―
4.教育のデジタル化―「新しい時代」を切り拓く学び―
この本をみた方に
おすすめの書籍
-
-
pickup
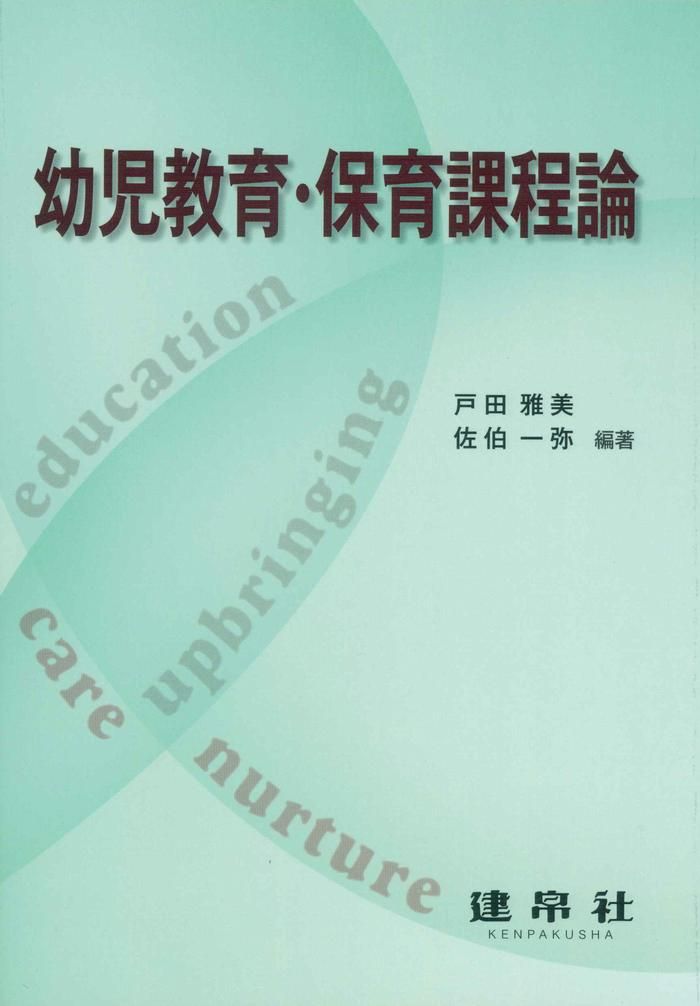
幼児教育・保育課程論
平成23年度より実施の保育士養成課程新科目にも対応した「幼児教育論」「保育課程論」のテキスト。保育の計画の基本や考え方,具体的な計画の立案の仕方を,事例を参考にしながら学習する。
-
-
-
pickup
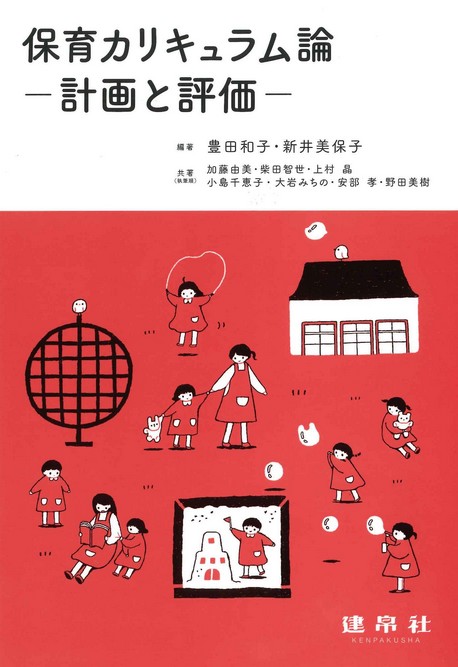
保育カリキュラム論―計画と評価―
2019年度から始まった新しい保育士養成課程の新科目「保育の計画と評価」の教科書。保育実践に役立つ充実した具体事例を多数掲載。幼保連携型認定こども園についても章を立てて解説する。
-
-
-
pickup
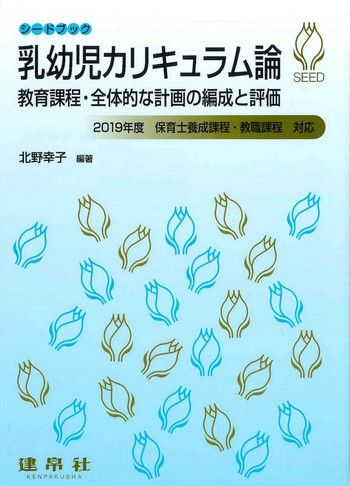
乳幼児カリキュラム論
教育課程・全体的な計画の意義と基礎理論,作成方法,実践力を高める工夫をまとめた。2019年度実施の教職課程・保育士養成課程に対応。
-
-
-
pickup
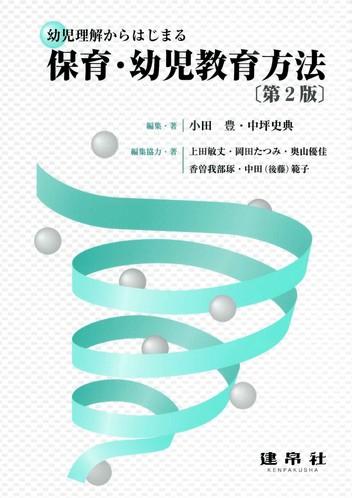
保育・幼児教育方法 第2版
まずは幼児を理解することからはじめよう。保育実践サイクルを活かした保育方法のテキスト。改定(訂)された指針,要領に対応した第2版。
-
-
-
pickup
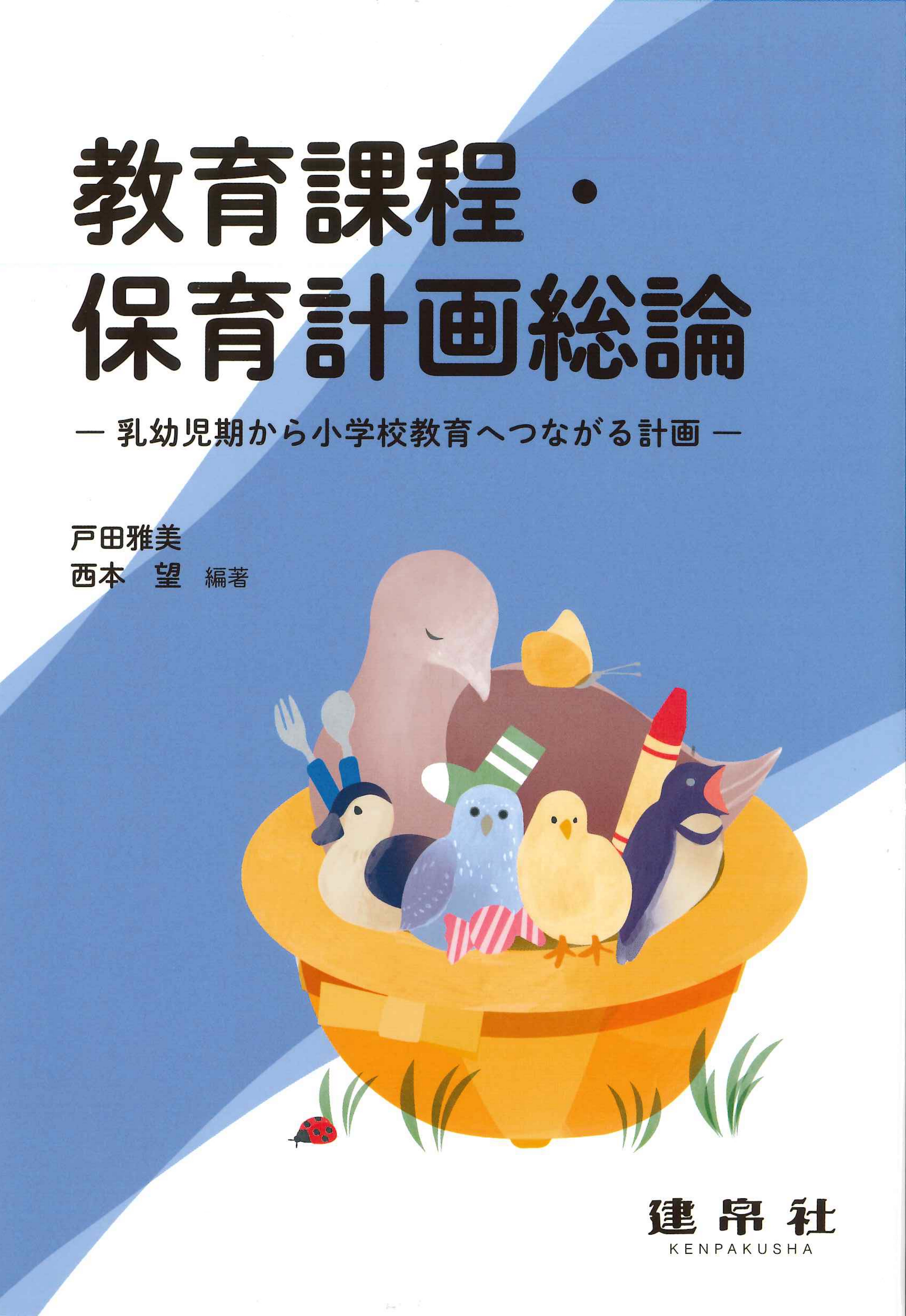
教育課程・保育計画総論
理論編と実際編の二部構成。理論編で法的背景や歴史など保育に必要な知識を習得し,実際編では豊富な計画例と解説を読み解くことで,保育実践の理解を深め保育をイメージできるようまとめる。
-
書籍に関する
感想・お問合わせ
下記フォームに必要事項をご入力いただき、一旦ご確認された上で送信ボタンをクリックしてください。
なお、ご返信さしあげるまでに数日を要する場合がございます。