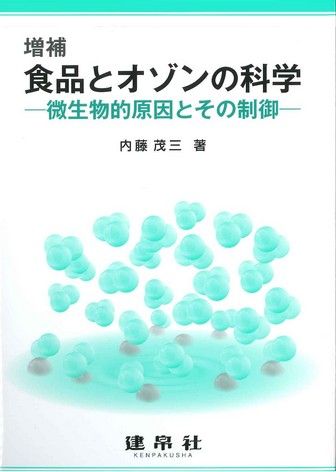平成31年1月1日
近年の食品工業へのオゾン利用
食品・微生物研究所所長 内藤 茂三この著者の書いた書籍
近年オゾン殺菌の利用が、活発になっている。従来の殺菌剤と異なり、大腸菌群等のグラム陰性細菌に対しての殺菌力が優れる特性を生かし、食品工場・病院厨房・レストラン厨房など幅広い分野で活用されている。従来の殺菌剤では殺菌できない微生物、いわゆる耐性菌が出現してきたため、殺菌の仕組みの異なる殺菌剤の導入が必要となり、オゾンが登場してきたという背景がある。また、残留しないので食品に使用しても表示の必要がない殺菌剤としても注目を浴びている。
さらに、最近、食品工場、病院厨房およびレストラン厨房で増殖して食品を変敗させる乳酸菌の汚染が問題となっている。乳酸菌は従来の殺菌剤や防腐剤に耐性があるが、オゾンでは容易に殺菌できる。オゾン水は濃度および発生量の調整が容易であること、さらに使用方法が容易であることから急速に衛生管理に用いられてきた。
また、オゾンは日本では古くから食品製造用剤として既存食品添加物リストにあげられ、世界に先駆けて認められている。オゾンを用いた衛生管理技術は日本で開発され発展してきた。利用技術は世界でも最も進んでおり、外国からの国内施設見学も多い。
オゾンは酸素原子が三つ集まってできており、通常の温度および圧力条件下では不安定な気体であり、容易に分解し、酸素分子と著しい酸化力を有する発生期の酸素となる。オゾンが分解したときに生じる発生期の酸素は非常に高い酸化力を有し、殺菌以外にも脱臭・漂白等に利用することができる。分子量は四十八と空気の約一・七倍の重さで、多くの食品工場では夜間のみ天井の配管から散布して殺菌している。
オゾンは空気中および水中に分散、または溶解した物質や微生物等に対して直接もしくは間接酸化、オゾン分解あるいは触媒作用で反応する。活性酸素原子によるオゾンの直接酸化反応は急速に進行するが、これは酸化還元電位が 二・〇七Ⅴと極めて高いことによる。水にオゾンを溶解したオゾン水(七つの溶解方法がある)は間接酸化反応でオゾンの一部はフリーラジカルを形成し、これが気中または水中に存在する微生物と反応して殺菌する。
オゾンは自然界にも存在し、高山・海岸・森林等の紫外線の強い午後一時から二時頃には〇・〇五ppmにもなる。
オゾンはどのようにして微生物を殺菌するのだろうか。その仕組みは、オゾンが細菌の細胞壁を直接攻撃して分解してしまう溶菌作用である。細胞壁を攻撃すると細胞壁のより易反応性の官能基と反応して細胞内に侵入して酵素等を破壊していく、構造的なものである。繰り返して使用しても耐性菌ができないのは、このマルチポイント攻撃のためである。一方、従来の殺菌剤である次亜塩素酸ナトリウムやエタノールは細胞壁を通過し、細胞内の特定の酵素を破壊するワンポイント攻撃である。このため繰り返し使用していくうちに耐性菌が生成する可能性がある。このようにオゾン殺菌の仕組みは従来の殺菌剤と異なるため併用できるという利点がある。
目 次
第109号平成31年1月1日
発行一覧
- 第122号令和7年9月1日
- 第121号令和7年1月1日
- 第120号令和6年9月1日
- 第119号令和6年1月1日
- 第118号令和5年9月1日
- 第117号令和5年1月1日
- 第116号令和4年9月1日
- 第115号令和4年1月1日
さらに過去の号を見る
- 第114号令和3年9月1日
- 第113号令和3年1月1日
- 第112号令和2年9月1日
- 第111号令和2年1月1日
- 第110号令和元年9月1日
- 第109号平成31年1月1日
- 第108号平成30年9月1日
- 第107号平成30年1月1日
- 第106号平成29年9月1日
- 第105号平成29年1月1日
- 第104号平成28年9月1日
- 第103号平成28年1月1日
- 第102号平成27年9月1日
- 第101号平成27年1月1日
- 第100号平成26年9月1日
- 第99号平成26年1月1日
- 第98号平成25年9月1日
- 第97号平成25年1月1日
- 第96号平成24年9月1日
- 第95号平成24年1月1日
- 第94号平成23年9月1日
- 第93号平成23年1月1日
- 第92号平成22年9月1日
- 第91号平成22年1月1日
- 第91号平成21年9月1日
- 第90号平成21年1月1日
- 第89号平成20年9月1日
- 第88号平成20年1月1日